廉思「蟻族」
キューブラー・ロス「死ぬ瞬間」
岩田健太郎「感染症は実在しない」
森博嗣「科学的とはどういうことか」
群ようこ「れんげ荘」
須田慎太郎・矢部宏治「沖縄の人はみんな知っていること」
梨木香歩「冬虫夏草」
マイケル・サンデル「それをお金で買いますか」
書評目次 書評2013← →書評2016
廉思「蟻族」
著者の廉思(Lian Si、リエン・スー)は中国の大学教授。中国にはチワン族、フェイ族、ミャオ族など、独自の民俗・習慣・言語を持つ少数民族が数多く存在するが、題名の「蟻(アリ)族」とはそうした少数民族ではない。中国の大都市郊外に多数存在する大卒低所得群居集団のことである。
最近、中国について個人的に最大の関心事だったのは、わがブログに対する恐ろしい量のスパムコメントであった。特に昨年後半からは、多い日には数十件ものスパムコメントが寄せられ、「最近のコメント」はすべてその種のもので埋め尽くされてしまったのである。
IPアドレスで規制したり、よく出てくる販促ワード(Louis Vuittonとか)で規制したりしたのだけれど、なぜかそういうのをすり抜けてくる。1日に何回もコメントを確認して削除して規制して、とやっていたのだけれど、さすがに時間と手間と気力が追いつかなくなってきた。最後は、従来のブログをあきらめて、新規のブログで更新することにしたのである。
その際に、IPアドレスから発信元を確かめたのだけれど、ご想像のとおり、大部分はChina Telecomで北京からアクセスされていた。IPアドレスの規制をすり抜けてきたのだから、個人ではなく少なくともグループによって、わがブログへの攻撃が行われていたということなのだろうか。全く、迷惑なことである。
個人的には結構な手間と時間がかかったこの事件を考えるヒントとなるのが、この本であった。
中国では、30年前には百万人程度だった高等教育(大学等)学生数が、今日では三千万人にも及ぶ。日本どころではない大卒者の急膨張に対して、就職先はそれほど増えていない。結果として、大学卒業後も故郷に戻らず、大都市近郊で低賃金労働をしつつ生活する人達が、少なくとも毎年数十万人単位で増えつつある。これが「蟻族」である。
蟻族は、北京や上海など大都市の近郊にある、群居村と呼ばれる地域に住んでいる。個人スペースはベッドだけという昔の学生寮のようなところで、プライベート空間はない。安普請で衛生的にもかなりひどいが、家賃は安い。彼らの平均月収は2000元弱というから3万円くらい。支出としては家賃に約350元(5000円)、食費に約500元(7000円)という。
彼らの仕事についても書かれているが、ほとんどが歩合営業など安定的なものではなく、しかも専門知識を求められるものでもない。しかし、彼らの知的レベルはきわめて高い。ただ大学を出ているというだけではない。彼らは故郷の学校をきわめて優秀な成績で卒業したエリートたちなのだ。
この本には、故郷の弟や親戚は普通に暮らして家庭もあるのに、自分は北京に出てこうして狭いところで貧しく暮らさなければならないなどということも書かれている。ベッド1つの生活から、わずかなチャンスをつかんでのし上がる人もいれば、1日中テレビゲームをしている人もいる。そして大多数は、チャンスのないまま年月を重ねるのである。
読んでいると、だんだん気が滅入ってくる。最も切ないのは、中国では高度成長が終わりに近づいてなお、この状況だということである。つまり、パイはこれ以上増えない。彼らのエネルギーを生活基盤の整備や社会資本の拡充に向かわせることができればいいのだが、中国は人口が多すぎて公共の意識が乏しいのが実情である。
日本でも、大卒やポスドクで就職先がないという話があると思われるかもしれないが、レベルが違う。森永くん(同級生だったりする)は年収200万円を低所得者としているし、実際アルバイトでもそのくらいは何とかなるが、月収15万円、およそ1万元は、彼らが理想として届かない収入なのだ。日本の安アパートと群居村のレベルも、また違う。
さらに言えば、公共施設のレベルは日本と中国では雲泥の差がある。個人的には広州と珠海しか知らないけれど、公共施設にウォシュレットのある国と、水洗どころかトイレもない住宅がある国とでは、人生に対する姿勢、世間に対する考え方は当然違ってくるだろうと思う。
私のブログにスパムコメントを入れる人達が、一件いくらの歩合でやっているくらいならまだ救いがある。少なくとも、彼らにはいくらかの収入になるからである。故郷から遠く離れた高学歴低所得の人達が、一攫千金の夢を抱いてスパムコメントを入れているとしたら、すごく気持ちが悪い。行き場のない思いが集まれば、それは呪いである。

[Feb 28, 2014]
キューブラー・ロス「死ぬ瞬間」
1969年に書かれたこの論文はその後に続編も発表され、わが国でも注目を集めた。ターミナルケアやホスピスなどは、この人に大きな影響を受けて今日の姿になった。その意義は十分に尊重するものの正直あまり関心がない分野だったのだが、ふと読んでみる気になったのは年を取ったせいもあるのだろう。
元の題名が” On Death and Dying ”だから、副題である「死とその過程について」がまさに著者の付けた題名である。だからこの本には、「死ぬ瞬間」のことなど書いていない。ざっくりと言ってしまえば、癌などの病気で余命宣告を受けた人が、それをどう受け入れていくかというとについて書かれている本である。
有名な「死に至る5段階」も、そういう文脈で理解する必要がある。5段階とは、1.否認と孤立(Denial)、2.怒り(Anger)、3.取り引き(Bargaining)、4.抑うつ(Depression)、5.受容(Acceptance)で、末期患者が混乱した状態から死を受容する状態に至るまでの経過をモデル化したものである。
著者自身も、すべてのケースが5段階の順序で現れる訳ではないと断っており、5段階の中には無理やり作ったと思われるものも含まれている。どうもアメリカ人は5段階が好きで、何でも5段階にする傾向があるのかもしれない。日本だと4段階(起承転結)にするのだろうけれど。
(キューブラー・ロスはスイスに生まれチューリッヒ大学で学んだが、米国人と結婚して渡米し、主な活躍の場は米国である。)
さて、この本のかなりの部分がインタビューやフィールドワークである。したがって5段階モデルも、患者の話を分類したり類型化するとそういうことが言えそうだというようにとらえられる。もちろん著者は医者であって病気や治療についてはプロなのだけれど、人間の生死そのものについてプロである訳ではないことに注意する必要がある。
おそらく、インタビューからあるモデルを作ってそれを一般化するような作業においては、「対象者(この場合は患者)が真実を語っていて」、しかも「聞き手が正確に相手の言いたいことを聞き取る」ということが必要であるが、それは医者だからできるというものではないと思っている。
極端なことを言えば、患者は真実など語らないし、聞き手は自分の聞きたいことしか聞かない。アメリカではフィールドワークというと御大層なもののように言うけれども、こうしたインタビューにしろ、カウンセリングにしろ、企業経営のコンサルティングにしろ、アメリカ由来の人対人の対応からすごいものが生まれてくるとは私は思っていない。
死に至るのはまさに時間の問題であって、長いか短いかの違いがあるだけである。おそらく「死ぬ瞬間」があるとすればそれは物理的な問題であって、自分のことだとすればなるべく痛くなく苦しくないことが望ましいというだけである。5段階があるとすれば自分自身ではなく、自分以外の誰かの死に対してではないかと思っている。
その意味では、医学的観点よりも宗教的観点の方が、この問題を扱うにはふさわしいということになるだろう。半世紀前の著作なので、あるいは言い古された感想なのかもしれないが。
終末期医療に関する古典的著作。ホスピスのあり方などに影響を与えた。

[Mar 14, 2014]
岩田健太郎「感染症は実在しない」
図書館で題名だけ見てトンデモ本かと思った。市立図書館の司書は面白い人達で、ときどきトンデモ本(何も食べなくても生きられる、とか)をさりげなく置いてあるのだ。しかし手にとってぱらぱらめくってみると、著者は大学病院の先生で内容も穏当である。借りて帰ってじっくり読んだ。
題名こそエキセントリックだけれど、主張していることはオーソドックスである。例えばインフルエンザを例にとると、「インフルエンザの症状が出ている」ことは「実態としてのインフルエンザ」にかかったことを意味しない。インフルエンザ以外の場合でも同様の症状が出る場合があるし、インフルエンザウィルスに感染したからといって症状が出るとは限らない。
世間の認識では、ウィルスへの感染イコール、インフルエンザであるが、そうした事例を勘案すると感染と症状は1対1の関係にない。したがって、感染症という病気が実在すると仮定するのではなく、現在出ている症状はどうやって治療するのがベストかと考えるべきであるという。これはもっともな主張で、どちらかというと常識の範疇である。
著者はここからさらに話を進めて、他の病気、がんであろうが糖尿病だろうが同じことだという。また、インフルエンザに話を戻すと、わざわざ費用と手間暇をかけてインフルエンザウィルスの感染有無を検査する必要があるのかどうか、そして感染して症状が出ているからといって、タミフル等を急いで処方する必要があるのかどうか疑問を呈する。
インフルエンザウィルスに感染したからといって100%症状が現れる訳ではないし、そもそもタミフルを飲んだ効果は治るまで5日かかるところが4日で済む程度とのことである。黙って寝ていた方がよっぽどいいということである。これは私自身も、常々疑問に思っていたことであった。
(ちなみに、がんや生活習慣病も同様のロジックが使えると書かれている。病名は、どちらかというと医者の都合で付けているとまで言っている。)
インフルエンザによる重篤な症状を避けるためには、むしろワクチンをきちんと接種すべきだということである。特に感染リスクの大きい医療従事者や、重篤化の可能性が大きい幼児にはワクチンが有効だということである。これもまた、もっともなことである。
そもそも著者が言うとおり、誰にとっても致死率は100%である。つまり、生きていれば必ずいつかは死ぬ。だから、どのように生きていくか。医療の側面から言うと、どうしてもなりたくないのはどの病気か、どういった症状なのかということが重要であって、これは患者にしか決められない。医者の立ち入るべき場所ではないということである。
手術や投薬などの治療行為において、医師は患者より段違いのアドバンテージと発言力を持っていると思われている。しかし他の専門分野と同様に、たとえ医師とはいえ専門家の一人に過ぎす、リスペクトはするけれども自分のことは自分で決めなくてはならないということである。そのことを再認識しただけでも、読む価値のある本といえるのではなかろうか。
近藤誠先生といいこの先生といい、医者に言われるままの治療に警鐘を鳴らす方はありがたい存在です。
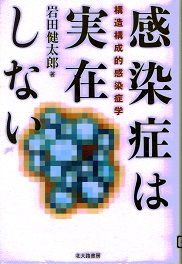
[Mar 28,2014]
森博嗣「科学的とはどういうことか」
2011年6月刊行の幻冬舎新書。したがって、昨今の理研騒ぎが起こるかなり前なのだが、こんなことが書かれていてびっくりした。
科学的とはどういう意味か。まず、科学というのは「方法」である。そして、その方法とは、「他者によって再現できる」ことを条件として、組み上げていくシステムのことだ。他者に再現してもらうためには、数を用いた精確なコミュニケーションが重要となる。また、再現の一つの方法として実験がある。ただ、数や実験があるから科学というわけではない。
個人でなく、みんなで築き上げていく、その方法こそが科学そのものといって良い。(本書107p)
また、こういう記述もある。
自分の考えたものだから、利益や賞賛を独占したい、というふうには科学者は考えない。「できるだけ、大勢に使ってもらいたい」「みんなの役に立てば、それが嬉しい」というような公開性、共有性に科学の神髄がある。社会の利益を常に優先することが科学の基本姿勢なのだ。
だから、科学的であるためには、常にそれを念頭に置かなくてはならない。意識していないと、他人にアイデアを盗まれないように秘密にし、自分だけがそれを扱えるように囲ってしまう。いわゆる「秘伝」というやつだ。(同138~139p)
まるで今日あることを予期していたような書きっぷりで、「だから言ったでしょ」と本人が言っていそうなところである。そして、ここに書かれていることは私自身もほぼ同意見であり、著者の先見性を認めるにやぶさかではないのだが、では「科学的」がそういう意味で使われているのかというと、やや違和感を覚えるのである。
科学が方法論であり、「間違いなく明らかであること」を基礎として積み上げていくシステムであることに異論はない。しかしそれを、共有性や公共の利益に結び付ける考え方は必ずしも共通認識とはなっていないように思う。それらはあくまで、「科学者に求められる資質」「科学のあるべき姿」であって、著者の個人的見解といえるのかもしれない。
私が思うに「科学的」とはもっと価値中立的なもので、誰か(あるいはみんな)の利益になるものでも、何らかの目的に沿って使用されるものでもない。世界の成り立ちについて、つたない人間の理性を基礎として積み上げるところの、はかない努力のようなものである。
ガリレオ・ガリレイの有名な言葉「それでも地球は回っている」がそれを端的に表現している。補足すると「(誰かにとって不利益になろうが、気に入らなかろうが)それでも、(私の理解する事実を積み上げる限り)地球は回っている(と考えざるを得ないし、おそらくそれが真実であろう)」ということだと思う。それが科学的という意味である。
科学的であることは、ときに世間の価値観と対立することがあるし、権力ににらまれることもある。ガリレオも教会に有罪判決を受け、キリスト教信者としての地位をはく奪された(中世においては「信者でない=市民でない」に近い)。そういう不利益を受けたとしても、物理原則や天体観測から得られた事実を説明しようとすると、地球の方が動いていると言わなければならないのである。
松戸出身のリケジョの場合、そういう崇高な理想に基づいたというよりも、世間の賞賛や政府研究機関のリーダーという社会的地位に目がくらんだということになりそうな気配である。言ってみれば科学的知見をカネに代えようとしたということなのだが、仮にそういうことであったとしても、科学そのものの罪ではない。そういうことをした人間が非難されるだけである。
科学そのものは価値中立的であるので、誰がどういう意図で使うかに関わらない。共有性とか公共の利益といったとたんに、そこには価値判断が入り込む余地がある。科学は1を積み上げて2をつくることができるが、1と2のどちらが偉いとか好ましいということには関知しない。それは科学に聞いても答えは出てこない。科学ではなく経済の問題だからである。
[Sep 20, 2014]
群ようこ「れんげ荘」
過去の書評を調べたら、群ようこの作品をこれまでとりあげたことはなかったが、実は作品のほとんどを読んでいる。千葉県出身の椎名誠の弟子だからである(「別人群ようこのできるまで」に書いてある)。この作品は、WEBの貧乏サイトで紹介されていたので図書館で借りてきた。大金持ちになった群ようこが貧乏話が書けるのかと思って読んだのだけれど、やっぱり書けてなかった。
まず気になったのは、月10万円で暮らしていかなければならないという主人公のリアリティである。作中には、「預金を取り崩していけば80まで持つ」ということなのだが、誰でも知っている大手広告代理店に25年勤めていれば(主人公はそういう設定)間違いなく年金受給資格がある。そもそも65歳から後は国民年金と厚生年金があるので、月に10万円以下ということにはならない。
そして、そんなにおカネがなかったら、なぜハローワークに行って失業保険受給の手続きをしないのだろうか。私の実体験から言っても、会社を辞めて最初にすべきは失業保険の手続きであり、次に勤めるかどうかとは別問題である。あえて行かないというのなら、なぜ行かないのか、説明がないとおかしい。
それと、「これで今月やっていかなければ」と銀行から10万円下ろしてくるのだが、手元の現金で10万円なら、家賃は?健康保険は?税金・年金は?公共料金はどうするのだろう?という素朴な疑問が最後まで解決されない。自分が貧乏生活をしているなら最も気になる点だし、毎月赤字なら通帳の残高が減っていくストレスは相当のものになるはずである。
その点について、続編「働かないの」にもう少し詳しく書いてある。家賃その他もろもろ含めて10万円という設定である。これで、税金や年金や健康保険料、全部払っているという。これは相当きついはずだが、主人公は喫茶店に行ったり外食したり銭湯に行ったり、古本屋行ったり自然酵母パンを買ったり除湿虫よけグッズを買ったり、親戚の子にプレゼントだ何だしている。いったいおカネはどこから出てきたんですかという話である。
師匠・椎名誠の「哀愁の町」では、アパートでは布団を干せないので、中川放水路の土手に干しに行く話があって、ここの部分はとても好きなのだけれど、狭い庭の1階で日当たりの悪いはずのれんげ荘なのに、なぜ外に洗濯物を干せるのか。師匠と弟子でリアリティに差がありすぎる。除湿器をフル稼働しないとやっていけないのに、食器を洗った後の布巾は乾くのか。「哀愁の町」ではそのあたりも細かく描写しているのに、「れんげ荘」にはそれがない。
そして、計算すると家賃が月に全部で7万円以下しか入らないのに(2階は老朽化して貸していないという設定)、なぜ不動産屋さんが掃除したりするんだろう。大家は固定資産税や不動産屋さんへの手数料を払って、正味いくら入るんだろう。一体何のためにアパートをやっているんだろう。どう考えても、普通は売ってしまって建て替える。都内の便利なところだそうだから。
また、家賃3万円という限界低家賃アパートなのに、住んでいるのは比較的常識範囲内の方々というのも現実離れしている。再び「哀愁の町」を引き合いに出すと、一晩中「おまえおまえおまえおまえおまえ」と言い続けるアルコール中毒の生活保護受給者みたいな人がいてもおかしくないのが現実であろう。せめて、1軒を数人でシェアする外国人労働者くらいいないと(そういえば、TRICKで仲間由紀恵はそんなアパートに住んでいた)。
はっきり書いていないけれど、主人公の持っている貯金は4千万円くらいと推測できる。それを使って、年間120万円で30年余りという計算のようだけれど、500万円くらいの中古公団住宅(首都圏でもいくらでもある)を買えば風呂もついて共益費7、8千円、貯金の残りと60歳から繰り上げ年金受給をすれば、家賃負担なしの月々10万円で問題なく暮らせるはずである。
私には、生活設計と優先順位付けができない主人公が、会社を辞めても同じような人間関係の中で同じようなことを考えて毎日を過ごしているようにしか読めなかった。まあ、群ようこ自身、若くして成功して大金持ちになり、何百万の和服を買ったり親兄弟に家を買ったり贅沢してたんだから、貧乏小説に期待する方が間違いだったということだろう。
群ようこの「無印」シリーズは何回も読み返したし「あたしの帰る家」も面白かったけれど、この作品はちょっと。貧乏サイトの人達も、なんでこれを誉めるのだろう。

[Nov 3, 2014]
須田慎太郎・矢部宏治「本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていること」
WEB上で誰かが薦めていた本なので(誰だか忘れてしまったのだが)、さっそくamazonで取り寄せて読んでみたところ、たいへん驚いた。正直なところ、目からうろこが落ちるとはこのことだろう。観光ガイドブックの体裁をとっているものの、すごい本である。
基本は、沖縄本島・離島に所在する米軍基地の概要・位置・役割・みどころなどの解説である。沖縄県内の基地、港湾、弾薬庫などについて書いてある。2ヵ月前に沖縄に行ってきたのだけれど、行く前に知っていればぜひ見てきたのに、という場所が結構あった。国道58号線を那覇から走っていて、普天間から北はすべて嘉手納基地だと思っていたらそうではないのであった。
まず基地関連で全く知らなかったのは、平安座島の石油備蓄基地が、もともと米軍への供給のために作られたということである。
あの施設は、オイルショックの教訓を踏まえ、石油の安定供給を確保するため国家プロジェクトとして作られたものだと思っていた(備蓄基地のHPにもそんなことが書いてある)。ところがこの本にもともと平安座は米軍関連と書かれていたので、さっそく調べてみると、確かにもともとのスタートが米軍支援目的であった。
計画自体もオイルショックのはるか以前(というより沖縄返還以前)に米国のオイルメジャーが計画し、土地を買収し埋め立て計画を立てたものであった(現在は日本企業の所有となっている)。石油の安定供給確保なんていうのは後付けの理屈であり、今日でも、米軍の使用する石油は、平安座島から対岸の送油基地を経由してパイプラインで各基地に送られているそうである。
施設解説以上に驚かされるのは、表題「本土の人間は知らないが…」と題したコラムである。自民党から政権を奪った内閣である細川内閣も、鳩山内閣も、不可解な早期退陣により政権の座から転げ落ちているが、それはすべて米軍絡みというのは、本当に沖縄の人にとっては常識なのだろう。というのは、かつて返還以前の時代に、何人もの首長が米軍のツルの一声で排除されていたからであった。
この本の中で何回か「米国政府はネコで、沖縄はネズミである。ネコの許す範囲でしかネズミは遊べない」という1946年、米軍高官の発言が引用されるが、この構図は戦後70年を経過しようとする現在もなお続いていることを沖縄の人間はみんな知っている。けれども本土の人間は知らないというのが本書の言わんとするところである。
その意味では私自身も同様であり、官僚支配とは何か、基地返還問題がなぜあんなにこじれるのか、この本を読むまで本当のところは分からなかったことを白状しなければならない。
観光ガイドの体裁をとってはいますが、なかなかすごい本です。正直、目からうろこが落ちました。

[Apr 26, 2015]
梨木香歩「冬虫夏草」
駆け出し文士の綿貫征四郎とゴローによる身辺雑記「家守奇譚」の続編。雰囲気は前作を引き継いでいるが、舞台は琵琶湖周辺から始まって鈴鹿の山中まで、広い範囲となっている。
この作者の以前の作品、「からくりからくさ」とか「沼地のある森を抜けて」とはかなり作品のトーンが違ってきているようだ。登場人物の性格も、作者の関心の範囲も、「家守奇譚」の頃とはかなり違っているように思う。その意味では、「家守奇譚」の続編というよりも、「海うそ」の続編と考える方がしっくりくるような気がする。
(「海うそ」は作品の舞台も登場人物も全く違うのだが、川に沿って山の奥深く入るところや、神仏分離に関する記述など、共通するところが多い。)
私自身も山歩きをするので、とても自動車では通れない山奥に廃村跡や廃屋を見ることがある。おそらく数十年前まではここに人が住んでいたのかと思うと、なつかしいような寂しいような、複雑な思いがする。鈴鹿の山奥にも多くの廃村があると聞くけれども、この物語はそれらの集落にも人々が暮らしていた時代を描いている。
この作品の白眉と言えるのが、イワナの宿の話である。愛知川の支流・茶屋川の奥深くにイワナの夫婦がやっている宿があるという。主人公はいなくなった飼い犬のゴローを探しに鈴鹿山中に向かうのだが、イワナの宿の話を聞いてぜひ泊まりたいとも思っているのである。これ以上はネタバレになってしまうので、興味のある方はお読みいただければと思う。
先日、奥多摩小屋でたいへんな扱いを受けたのだけれど、その時思ったのは、イワナでさえちゃんとお客をもてなそうという心がけがあるのに、人間がそれをできないというのはどういうことだろうということであった。
私も最近歳をとってきたのか、意思の疎通ができるのは宇宙万物すべてではないのだろうかなどと考えたりする。その一方で、どうしても共感できない「人間」がいるというのも寂しいことである。
そういう意味では、前作「家守奇譚」でも動植物などとの交流が描かれていたのだが、今回はそれらに加えて神仏、精霊、過去と未来などさらに範囲が広がっている。いろいろと考えさせられる作品で、ここ2ヵ月で、もう4、5回読み返している。
この作者の作品は、トーンが変わってもなぜか違和感なく読めます。不思議です。

[May 11,2015]
マイケル・サンデル「それをお金で買いますか」
原題が“What Money Can't Buy”(お金で買えないもの)。副題が「市場主義の限界」、2012年に刊行された。いまや史上主義全盛でネオコンがわが世を謳歌している時代であるが、なんでもカネで解決するんじゃないと著者は世の中の趨勢に異議を唱える。この本の主たるテーマである道徳的・倫理的側面の大切さはもちろんであるが、いろいろ考えさせられた本であった。
考察するテーマは、1章から順に「行列に割り込むこと」「インセンティブ」「友情・謝罪」「生命保険」「名誉と祝祭」である。いずれの分野においても、かつては人間として当たり前だったことが、現代では急速かつ圧倒的に市場経済に浸食されている。何でもカネで解決するのが当り前という今日の風潮も、もともとそうではなかったというのが本書の共通のテーマである。
第1章の「行列に割り込むこと」については、テーマパークにおけるVIPのような露骨な例から、空港における保安検査のように顧客差別化と紙一重な例まで考察される。今日では、カネを多く払えば割り込んで当り前という考えが一般的になりつつあるが、そもそも割り込みは道徳的・倫理的に許されないことであった。カネを持っていれば割り込めるというのは、ここ20年位のスタンダードなのである。
次の章では、インセンティブ=経済的利益、負のインセンティブ=経済的不利益だと現代人は考えているけれども、行き着くところ、罰金と料金の区分が不明確となるがそれでいいのかという点が指摘されている。
「ルールを破れば罰金を払わなければならない」イコール「罰金を払えばルールを破っていい」ということではない。けれども、現代においては徐々に後者の考え方が優勢になりつつあると本書では指摘する。それでは、もともとの要請である「共同体の構成員はルールを守らなければならない」という規範がないがしろになるという。そのとおりである。
続く第3章では、友情や謝罪はカネで買えるのかという点が考察される。結婚式で他人に書いてもらったスピーチ原稿を読むことは許されるのか、真摯な謝罪であれば本人でなくてもいいのか。今日では(日本でも)、よほどの重大事故でない限り自動車事故の後処理は保険会社任せである。本当に友情や謝罪はカネで買えないと言えるのか、考えさせられる。
このあたり、訳がよく分からなくて読みづらい部分もあった。「前者の場合、金銭的取引を通じて買われる善が台無しになってしまうのに対し、後者の場合、善は売られてもなくなりはしないが・・・」(138ページ)といった具合である。この「善」の原文はおそらくgoodsで、商品、財と訳すべきところである。それが分かって、大分と読みやすくなった。
第4章で、もともと保険とは、貿易において船荷が無事目的地に着くかどうかという海上保険から始まったもので、生命保険の歴史は比較的新しい。その背景には、人の命を賭けにしていいのかという倫理的問題があったことが説明されている。
この倫理的問題を解決するため、生命保険においては、被保険者の死亡により経済的に問題を抱えることになる者が受益者でなければならないという縛りがあった。だから、家族や被扶養者が受取人である生命保険は比較的早くから認められたのに対し、それ以外の第三者が受取人となる生命保険は多くの人から嫌悪感を持たれており、実際に商品化されたのは最近のことである。
今日、その縛りはかなり緩やかなものとなっており、企業が従業員に保険をかけることは珍しくなくなっている。さらに、生命保険の買取や証券化もすでに行われつつあり、全くの第三者が、他人の余命の長短により運用益を得るという事態が現実味を帯びてきている。それは、他人の命をタネに賭けていることと違わないのではないかというのが本書の指摘である。

前回は、海上保険からスタートした保険業務が、生命保険に範囲を拡大し、当初は厳しかった道徳的倫理的な縛りが時代とともに緩く拡大解釈されるようになったきたこと、さらに、生命保険が証券化されることにより、結果として他人の余命次第で運用益を得る状況、つまり他人の命の長短をタネに賭けをするような状況となりつつあるというところまで話を進めた。
このあたりを読んでいて、全く本筋とは関係ないのだが、昔、銀行にいた頃、輸出手形の買取りを山ほどやったことを思い出した。もう30年以上も前のこと、銀行の支店業務で外国課に配属された私は、来る日も来る日も、輸出手形買取りという仕事をやらされたのであった。
輸出手形の買取りとは、海外に商品を輸出する会社の資金繰りのため、船荷を担保としておカネを貸すことである。というとリスクがかなりあるような気がするけれども、先方は大抵の場合、銀行発行の信用状(Letter of Credit, L/C)を送ってきていて、そのL/Cに記載されている書類が揃っていれば、仮に船荷に不具合があったとしても銀行から支払を受けられるという仕組みになっている。
したがって、輸出手形の買取り業務においては、輸出会社、輸入会社の信用とほとんど関わりなく、L/Cに書いてあるとおりの書類が整っているかどうかに集中しなくてはならない。Invoice 2setと書いてあるのに1setしかなければ不払いの理由になるので数を揃えるし、B/L(船荷証券)やInsurance(保険証券)のサインが抜けていれば取ってきてもらうしで、なかなか神経を使う仕事なのであった。
そして、チェックしなければならないポイントのうちかなり大事なものが、金額がFOBなのかCIFなのかということなのである。同じ10000ドルの商品であっても、それがFOB Osakaであれば船賃・保険は先方持ちなのでそういう書類になるし、CIF HongKongであれば船賃・保険はこちら持ちである。それがL/Cに書かれている条件と違うとなると一大事なのである。
だから、この本を読んでしばらくの間は、かつての記憶が頭の底から浮き上がってきて、FOBとかCIFとか、Freight PrepaidとかFreight Collectなどという言葉が、脈絡なく脳裏に浮かんできて困ったのでありました。
最後の章「名誉と祝祭」においては、まずノーベル賞はカネで買えるか、もし買えるとしたら今日われわれがノーベル賞に対して持っている敬意が失われないかというところから議論が始まる。そして、現代ではスタンダードとなっている「命名権」についても、本当にそれでいいのかという疑問を投げかける。
確かに、「味の素スタジアム」くらいなら、味の素ならスタンド作るくらいできるだろうなと思うのだが、ボディーメーカーコロシアムだのエディオンアリーナなどと言われるとなんだそれと思う。税金で作ったものを民間会社の宣伝に使っていいのかという問題もある。そしてこの本で指摘しているのは、そもそも祝祭に関するものはカネになじまないということである。
スタジアムで観客が一緒になってひいきのチームを応援するというのは、共同体の構成員相互の連帯感を高めるというのが本来の趣旨である。だから、昔のスタジアムにはVIPラウンジはなく、チームのオーナーであっても吹きさらしの客席で応援すべきものとされていた。それが今日では、スポーツチームの収益のかなりの部分がVIPラウンジ収入なのだそうである。
現代においては、スポーツを応援するのも文化活動を楽しむのも個人の消費活動として誰も疑わないし、提供する側も商売だとみんなが思っている。しかしそうした活動は元来、共同体の連帯感を高めるために行われてきたし(典型的なのは「祭り」)、誰かが商売するために行われてきたものではないと本書は指摘する。
こうした著者の指摘はそれぞれにうなずくべき理由があり、論旨も根拠も明確である(不足があるとすれば日本語訳)。とはいえ、この本を通して読んでみて思ったのは、カネで買うべきでないものを売る人がいて買う人がいるのは悲しいことだけれども、ある意味あきらめる他はないということである。
カネ(貨幣)というのは幻想であり、多くの人がそこに価値を認めるから実体化するのだという説がある。歩きながらスマホでゲームしてポイント(ゲームの点数)を貯める人にはその行為に意味があるのかもしれないが、私にとっては意味がないしほとんど価値もない。危なくて邪魔なだけである。
生きる上で必要であるのは、カネの先にある財でありサービスであり、それらに付随する価値である。カネ=価値ではないし、価値を得る手段は狭義のカネだけではないはずである(例えば時間であったり能力であったり)。それを踏まえた上で、自分がどういう行動をとり何を優先するのかを判断していけばいい。市場万能主義をムキになって否定するよりも、静かに遠ざけるという姿勢が望ましいのではないかと思ったりする。
市場経済がすべてに優先するという価値観を痛烈に批判した本。生命保険や命名権の問題も含めて、改めて検討すべき課題だと思います。

[Dec 30, 2015]