宮本常一「忘れられた日本人」
井上靖「しろばんば」
野口悠紀雄「金融危機の本質は何か」
石弘之「感染症の世界史」
ブライアン・サイクス「イヴの七人の娘たち」
稲垣えみ子「魂の退社」
高橋大輔「漂流の島」
筒井功「日本の地名」
書評目次 書評2015← →書評2018
宮本常一「忘れられた日本人」
最近5年間くらいに読んだ本の中で、腰が抜けたというか、目から鱗が落ちたというか、最高にすごかったのはこの本である。
この本は、宮本常一が全国各地でその土地の古老から聞き取り調査をしたり、その過程で起こったさまざまなことについて記録したものである。多くは昭和20~30年代に発表されたもので、内容としては明治時代初期の日本の農村の姿であるから、ところどころ古い言葉が使われている。それでも決して読みにくくないのは、宮本の説明がたいへんに巧いということである。
宮本常一は民俗学に独自の境地を開いた人としてたいへん有名なのであるが、あまり好きではない網野善彦の師匠筋にあたるものだから、これまであまり食指が動かなかった。ところが、ふと思い立って読んでみたところ、網野善彦とは違って読みやすいし、主張を抑えて自分が何をどう聞いたかということを淡々と書いているのが好ましく感じた。
まず最初は対馬の話である。戦後間もなく発足した九学界連合(人類学・民俗学・言語学・考古学等関連する9学界が相互啓発や学術交流を図る目的で設立。元大蔵大臣・日銀総裁である渋沢敬三=宮本のスポンサー、の肝煎り)の対馬調査において、本題である調査の内容よりも興味を引かれたのは、資料を貸し出してもらうまでの村人との折衝である。
古くから伝えられている文書を見せてもらうのに、鍵のかかった文書箱を開けてもらうまでが一苦労。だが、徹夜で内容を写したけれども終わらない。しばらく貸してもらえないかと頼んだところ、それは寄合いに出かけている息子に聞かなければ分からないと言われる。そこで息子さんを呼んでもらったのだが、「そういう大事な問題は寄合いにかけて皆の意見を聞かなければならない」と言われてしまうのである。
その後、寄合いに出かけて行って、そこでこう言われて・・・とさらに話は続くのだけれど、ここで明らかになるのは、日本社会の意思決定の過程というのは、そもそもこのようなものだったということである。おそらく作者である宮本常一は、かなり意識的にこの話を挿入している。というよりも、このような本題からやや外れたところに、民俗学の重要な視点がちりばめられている。
昨今、わが国においては意思決定の迅速化が官民ともに重視されているようである。その流れの中にあって、わが国がもともと持っていた意思決定方式である全員参加・全員納得というやり方が捨てられてしまっている。しかし、昔からこういう方法が踏襲されてきたということは、他のやり方でやってもうまくいかなかったということではないだろうか。
少なくとも聖徳太子の十七条憲法には「大事なことは一人で決めてはならない」と書いてあるので、7世紀にはすでにそうだったということである。私が思うに、それは縄文時代(約1万年前)からずっと受け継がれてきた日本社会固有のルールなのである。「待ったなし」とか「バスに乗り遅れるな」とか言っているのは、せいぜいここ2~30年のことである。
対馬の話以外にも、宮本常一が全国の村落を歩いた記録が収められているが、この本の中で最も有名なのは「土佐源氏」である。
この作品は、土佐の山奥にある檮原(ゆすはら)という村で、橋の下に小屋掛けしている乞食から聞き取ったという体裁になっているが、佐野眞一「旅する巨人」(渋沢敬三と宮本常一を題材としたノンフィクション)で書かれているように、この話の大部分は不正確というか虚構(フィクション/作り話)である。
それが、乞食を装った話者の作り話なのか、宮本常一の作り話なのか、あるいは戦争で記録が焼失したことによる記憶違いなのかということは分からないが、いずれにせよ、そうなると学術論文の形式とは若干離れていることは否定できない。(出版社の企画物記事として編集されたものなので、サービス精神を発揮したのかもしれない)
しかし、はじめに書いた対馬の話と同様、「土佐源氏」の中には話の本筋以外のところで、古い日本のしきたりや習俗が多く記されている。仮に本筋の話が虚構であったとしても、宮本常一がこうしたことを書き遺した意義は非常に大きいと考えられるのである。
網野善彦の師匠筋なので食わず嫌いしていたら、すごくいい本でした。古き良き日本を知る上で必読だと思います。

[Mar 28, 2016]
井上靖「しろばんば」
小学生の頃はじめて読んで以来50年、折に触れて読み返している本である。まさか伊豆に転勤になるとは思わなかったから、改めて読み返している( 同じような本としては「吾輩は猫である」がある)。
主人公の洪作は、井上靖が自分のことを書いているとされる。時代は大正年間、事情があって祖父のお妾さんで、羽振りのよかった祖父が下田の芸者を身請けしてきたという「おぬい婆さん」と暮らす彼は、伊豆の山奥、天城湯ヶ島の土蔵で暮らす小学生であるが、そうした環境もあったのかどうか相当の自意識過剰である。
洪作の周りで起こる事件は、なんということもない日常的なものである。いまの時代と似たようなことも結構あるものの、大正時代のことであるから、神隠しの騒ぎがあり、結核で若くして亡くなる人がいて、そういう時代だったことが分かる。そして、いまの私の境遇上うれしくなってしまうのは、おぬい婆さんと洪作が馬車に乗って豊橋の父母の許を訪れるくだりである。
「街道の左手に見えたり隠れたりしている狩野川」は私の住んでいる借上げ社宅のすぐ横を流れているし、「馬車の終点である大仁部落へはいる手前で、馬車は大仁橋という大きな橋をわたった」の大仁橋は、週何回か通っているスポーツクラブのすぐ近くである(頑丈なものに架け替えられているが)。
「馬車は終点の大仁駅前で停まった。ここから軽便鉄道が三島町へと走っていた」の軽便鉄道は、伊豆箱根鉄道駿豆線になって修善寺まで伸びている。大仁駅には、地元温泉旅館の名前がはいったタイル貼りの水飲み場があって、往時の雰囲気をいまに伝えている。しかし、軽便鉄道だった頃とは異なり、いまでは東京まで直通の特急踊り子が走っている。
そんなふうに楽しんで読んでいたら一冊終わってしまった。あれ、この本には石川啄木の短歌が出てきたり、教師が自殺騒ぎを起こしたりするんじゃなかったかなと思って「あとがき」を読んでみたら、なんといまの子供向け「しろばんば」の本は前半だけで、後半は載っていないのだった。改めて少し上の年代向けの本を借りて続きを読んでみた。
(ちなみに、この前半・後半というのは便宜的な区分けではなく、1960年に主婦の友に連載された時の題名が「しろばんば」「続しろばんば」だったことによるそうである。)
すると、昔読んだ記憶が次々とよみがえってきた。つまり、深く記憶に刻み込まれている名場面は、前半よりも後半の方が多かったということである。あいかわらず洪作は自意識過剰だし、村の子供たちに対する上から目線も気になるところであるが、それなりに責任感らしきものがあるし、弱者に対するやさしさもうれしいことである。
そして後半でも、シイタケ栽培の話とか、伊豆長岡から三津(みと)に抜けていく道の話とか、伊豆に住んでいる者の琴線に触れる話題が満載である。シイタケは現在でもわさびと並ぶ伊豆の名物で、修善寺のアジ寿司屋ではシイタケ弁当も売っている。
そして、物語のフィナーレ近く。おぬい婆さんが亡くなって洪作は父母とともに豊橋に移ることになるが、このあたり井上靖の筆はまさに神がかり的で何度読んでも圧倒される。あまりつきあいのない親戚の人やご近所、土地の知り合いのほとんどすべてが、最寄りのバス停まで見送りに来る。わが国のおける旅立ちは、もともとそういうものだったのであろう。
さて、今回のあとがきを読んでいて知ったのだが、この「しろばんば」にはさらに続編があって、青年になった洪作が柔道に打ち込むという内容なのだそうだ。そして、その柔道というのが、講道館ではなく高専柔道なのである。高専柔道といえばあの木村政彦とも縁が深く、いまのグレイシー柔術につながる伝統の格闘技である。
家業である医師をめざすべく勉学に励む洪作が、なぜ高専柔道に行ってしまったのか、これは何としても続編を読まなければならなくなった(ちなみに、井上靖本人も高専柔道の経験があり、実際に医者にはならず新聞記者となり、さらに作家となったのは中年を過ぎてからである)。
井上靖本人が、「私の作品がすべて読まれなくなったとしても、しろばんばだけは残るだろう」と言ったそうだ。残ってほしいという願望でもあるだろう。風林火山も残りそうだが。

[May 12, 2016]
野口悠紀雄「金融危機の本質は何か」
図書館で本を探して歩いていて、ふとこの本が目に止まった。2009年の本だからそれほど新しくはないが、それほど古い訳でもない。サラリーマン生活も終わりに近づいて、野口先生の本に目が止まるというのも、何かの縁だろう。
野口先生はこの世界では知らぬ者のない大先生で、東京大学、早稲田大学、スタンフォード大学などで教鞭をとられており、また「超」整理法など軽い本でもベストセラーを持っているのであるが、私が教えていただいたのはそれより前、まだ先生が一橋大学に行って間もない頃のことであった。
その頃は第二次オイルショックとバブルの中間期で、日本企業もまだまだ地力をつけなければならないとまともに考えていた時期であった。当時、企業が入社して間もない若手職員を集めて、いろいろな教養講義を行う「背広ゼミ」というのが流行していた。野口先生はその講師であり、私は10名ほどいたゼミ生の一人であった。
まだ週休二日になっていなかった頃だから、時代がひとつ違っていた。ウィークデイに週1回、夜7時か8時からやるのだけれど、仕事が終わらなくて来れない人も結構いた。いま考えると、入社3年以内の新人に残業させなければならない仕事などありえないのだが、当時はそういう時代だったのである。私だって歩積両建でさんざん休日出勤したくらいである。
期間は半年くらいだっただろうか、その最後には会社の保養所に泊まり込みで、最終ゼミというのをやった。もちろん、食事も宿泊費も会社持ちである。私は出席率がかなりよかった(確か全部出席のはずである)こともあったのだろう。先生に、「△△さん(私のこと)、留学するなら、私が推薦状書いてあげますよ」と言われたことを思い出す。私の黄金時代であった。
後から考えると、野口先生は大蔵省出身、私の職場は銀行だったから、おそらくそういうルートがあってかなりの高額報酬でお招きしたのだろう。でも、そういった役所と業界の関係的なこととは全く関係なく、先生は自分の実力で現在の地位を築き上げた。たいへんなものである。それに引き替え不肖の弟子は、少しでも目をかけてもらっただけの精進はしなかったのであった。
野口先生の専門は経済学だが、もともと理系の出身で、数学的なバックグラウンドに立って考察される。私の頃にはまだ「マルクス経済学」が力を持っていて、大学の講義も先生方も、半分とはいかないまでも3分の1くらいはマルクス経済学系であった。しかしながら私は、数学的な考え方が好きで、大学のゼミも統計学だったし、先生も理系出身の先生と相性がよかった。
(そういえば、家の奥さんがTVタックルを見ていたら、高橋洋一が「統計的には・・・」と何度か言っていたそうだ。彼は私のゼミの同期生である。)
それから約40年、マル経はどこにいってしまったんですかという世界だし、野口先生の守備範囲である金融工学やファイナンス理論は全盛である。全盛を通り過ぎて、弊害が目立っているという世論に対してこの本は書かれていて、金融工学のせいで株価が乱高下し景気の足を引っ張るなどというのは、とんだ言いがかりであるというのがこの本の趣旨である。
野口先生にしては、あまり数式は出てこない。それもそのはず、この本は東洋経済の連載記事をまとめたものであった。けれども、「金融工学は、リスクが小さく利益率の高い投資を約束するものではない」「うまい話には裏がある」「やたらと数式を使って丸め込もうとする奴らは、嘘つきである」といった常識を繰り返し述べているのは、さすが野口先生である。
現在に至る金融危機の本質は、プライシング(価格付け)が正当でなかったことで、これは、分からないことを分かると言ってセールスした側に問題があるとともに、本来、そうしたことにブレーキをかけるべきであった人々が、分からないことを分かったふりをして推進してしまったことに原因があると先生は指摘している。
そして、先生が若い頃、この道の権威という先生方(個人名も大体見当がつく。当時大蔵省に顔の利いた先生方だ)から、「若造が分かったようなことを言うな」と言われたことや、米国留学中の思い出、エデンの東の話などいろいろな話があって読み飽きないし、ケインズやフリードマンなど経済学の重鎮に関することなど、豊富な話題が盛りだくさんである。
さすがに野口先生、いくつになっても弟子は教えられることばかりです。
[May 25, 2016]
石弘之「感染症の世界史」
現在の印西市は旧・印西市、本埜村、印旛村が合併してできた。もともと本埜村住民でも印西市の図書館カードは作れたので旧・印西市の図書館から本を借りることはできたが、印旛村の図書館で借りられるようになったのは合併後である。
図書館によって、揃えている本や開架してある本に違いがあるのはおもしろい。印旛村図書館の場合は、日本医大北総病院(救急救命ヘリのロケ地)があるため、病気に関する図書が充実している。日野原重明先生の本が多く置いてあるのもおもしろい。
最近、そうした本を借りてきて読んでいるのだが、現役のお医者さんの書いた本はいまひとつ頭に入ってこない。もちろん文系頭と理系頭の違いがあるし、年々脳の働きが鈍くなっているのでそこは仕方がないとしても、議論の厳密性に重点を置きすぎて、読者が知りたいことをまっすぐ書いていないように感じるのである。
例えば、薬品の実効性について議論する場合、目隠し検査でプラシーボ(偽薬)との違いが統計的に検証されなければ有効とはいえないというのはその通りだが、われわれが知りたいのは、その薬品を投与しなければ何%の確率で症状が重篤化するか、それに対して副作用は何かということであって、統計的な厳密性は二の次の問題である。
その点でこの本は面白かった。著者はお医者さんではなく元朝日新聞の編集委員で、どちらかというと新聞記事的な書き方をしているからだろう。特に、タミフルは人体から下水を通ってすでに自然界に拡散されているので、宿主である鳥の体内でタミフル耐性インフルエンザウィルスができているに違いないなどという話は、統計的な裏付けはないとしても興味深い。
題名のとおり、この本では人類はじまって以来の感染症である天然痘、ペスト、コレラ、結核、インフルエンザからエイズ、エボラ出血熱、デング熱に至るさまざまな病気の流行の経緯、感染源の考察、今後に向けた教訓等を述べたものである。
天然痘は平安初期に大流行したくらいだから、有史以前からある感染症なのかと思っていたら、東洋に入ってきたのはシルクロード経由で東西貿易以降ということだから、まだ二千年くらいしかたっていない。そして、コロンブス以前には、米大陸の原住民の大多数は多くの感染症に免疫がなかったので、感染症によって大打撃を受けたことがインカやアステカが滅亡した原因となったという。
この本を読んで改めて認識したことが2つある。一つは「諸行無常盛者必滅」ということ。人類の歴史において、感染症が原因となって、それまでの人口が半分、極端な場合10分の1以下になることは決して珍しくないことである。だとすれば、これから未知の感染症が大流行してそうした事態になる可能性はないとはいえない。
じっさい、ウィルスの中にはもともと動物にだけ感染するけれども、突然変異によって動物から人間に感染し、さらにヒトからヒトに感染するようになったものが結構ある。そして、そういうウィルスに限って致命的なのである。いまPolitical Correctな観点から人間の移動に制限はかけられない状況になっているから、ひとたび流行すれば鎮圧化は容易ではない。
一方で、いかにウィルスが致命的であっても、遺伝情報としては人間に比べると単純なものしか持っていないので、全人類の何割かは、もともとそのウィルスに感染しない、感染しても発病しないのだそうである。
かつて大変な騒ぎとなったエイズにしても、高リスク集団の中にあってなぜか感染しない、発病しない人達の存在は知られていたそうだし、エイズに限らず、ほとんどの感染症でそうしたケースは認められている。最近の研究では、遺伝情報にさまざまなバグがあって、そのバグゆえに感染しないこともあるという。
そうなると、まさに「人間万事塞翁が馬」、何がラッキーで何がアンラッキーなのかは、「棺を覆いて定まる」としか言いようがなくなる。適者生存という言葉自体、何に対して適しているのかということが常に変わる可能性があるということなのである。
旧・印旛村の図書館には医学関係の本が揃っていて、これもその中の一冊。感染症が人類に及ぼした多大な影響について考察している。
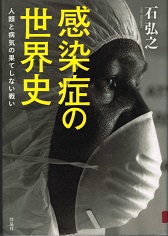
[Nov 9,2016]
ブライアン・サイクス「イヴの七人の娘たち」「アダムの呪い」
ブライアン・サイクスは英国の分子遺伝学者。オックスフォードの分子医学研究所で、世界中の人種や化石から採取したDNAを分析して、人類がどのようなルートを通じて現在の形になったのかを研究している。
今回あげた2冊の本は「イブ」がミトコンドリアDNAの分析、「アダム」がY染色体DNAの分析で、いずれもここ20年で急速に研究の進んだ分野である。ちなみに、ミトコンドリアDNAは母親から子供にしか伝わらないし、Y染色体は父親から息子にしか伝わらない。著者はミトコンドリアDNAに注目した最初の研究者である。
サイクスをはじめとする分子遺伝学の成果、つまりDNA分析により現代人の共通祖先が存在した年代を推定したり、化石やアイスマンのDNAを復元して現代人と比較したりする研究により、それまで現代人との関わりが不明であったネアンデルタール人が絶滅したらしいことが分かったり、現生人類がアフリカから各大陸に広がったことが証拠づけられたりしている。
この本を読み始めた時に思い出したのは、かつて深く研究した競走馬の血統についてである。われわれが若い時には、競走馬の父系(サイアーライン)をたどると3頭の馬になるというのが血統研究の「はじめの一歩」であった。いずれも1700年代、いまから300年前の馬で、ダーレーアラビアン、ゴドルフィンアラビアン、バイアリータークの3頭である。3大始祖という。
実際に日本の競馬においても、クライムカイザー(ゴドルフィンの子孫)やシンボリルドルフ(バイアリータークの子孫)などのダービー馬が1970年代までは出ていたものの、2016年の現在、生産されている馬の99%以上はダーレーアラビアンの子孫である。おそらくあと50年もすれば、日本のみならず全世界のサラブレッドの父系祖先はダーレーアラビアンのみということになるだろう。
そして、ダーレーアラビアンの父系で現在残っているのは1764年生まれのエクリプスの子孫が99%である。そして、そのほぼ半分が1935年生まれ(たった80年前!)のネアルコだから、もしあと200年競馬が続いていれば、全競走馬の父系をたどるとすべてネアルコという時代になるかもしれない。
一方で、母系(ファミリーライン)というのは数多く残っていて、日本だけでも何百というファミリーがある(輸入馬がいるので年々増える)。全世界となると数千数万というオーダーになると思われる。これは、種牡馬が1年で百頭以上の種付けが可能であるのに対し、繁殖牝馬は1年に1頭しか産めないから、そんなに急には収斂されないのである。
人間もきわめて長期間のスパンをとれば、同様に父系・母系とも数少ない共通の祖先にたどり着くというのが本書の指摘するところである。「イブ」では、ヨーロッパ人の母系祖先をたどると7人の女性に収斂するという(全世界では、いまのところ35人になるらしい)。
さて、それぞれの本であるが、「イブ」の方は著者がミトコンドリアDNAによる分析に着手してから7人の共通祖先に至る経過を時系列的にたどるもので、臨場感があって面白い。当初は(といっても20年くらい前の話)ミトコンドリアDNAが信頼できるものかどうかから議論されているので、いまの科学の水準を知る上でも有益である。
一方の「アダム」は、もともと著者がY染色体の先端研究者ではなかったので、ある意味、知っていることを書いただけという見方もできる。本を面白くするためもあっていろいろと大胆な推論をしているのだが、ちょっと首をひねるところも少なくない。著者はそうではないと言うだろうが、いわゆる竹内由美子的な書き方である。
すべての男性がY染色体の命じるままに=本能のままに行動しているという指摘はともかくとして、私的所有は農耕以降に発生したもので、それによりY染色体の淘汰が始まったというような推論がなされているが、私的所有はそれこそ石器時代だって土器時代だってあったと思う。財産ということでいうなら、余剰生産物があるかどうかが重要で、農業生産に限らない。(→1.5.3 富の蓄積と余剰生産力により領土拡大は意味のあるものとなった。)
ということで、どちらかというと「イヴ」の方をお薦めするものであるが、最先端の人類学についていろいろ勉強になることは間違いない。
分子遺伝学の成果により、個人個人のDNAを調べれば、誰と親戚でどのような来歴により今日に至ったか、分かるそうです。知りたくもあり知りたくもなし、といったところでしょうか。

[Dec 14, 2016]
稲垣えみ子「魂の退社」
この書評も、最初は1970年代のなつかしの少女コミックス中心だったのですが、最近は字だけ書いてある本が多くなりました。今年も関心のある分野を折に触れて紹介したいと思いますので、よろしくお付き合いください。
さて、この本じつは私でなくて奥さんがリクエストして買った本である。昨年夏、図書館に予約したにもかかわらず年末まで順番が回って来なくて、めんどくさいから買ってしまった。買った以上、私も読んでみたのである。
著者は、新卒以来長年勤めた朝日新聞を50歳を機に退職、新生活に踏み出したのであるが、最初の方で述べられている会社を辞めた理由が、昨年7月でリタイアした私とほとんどかぶるのである。同じように感じるのは私だけじゃないんだと改めて思ったものである。(私の退職については、これとかこれをお読みいただければ)
特に、「会社で働くということは、極論すれば、お金に人生を支配されるということでもあるのではないか」とか「その結果どうなるか。自由な精神はどんどん失われ、恐怖と不安に人生を支配されかねない」といったあたりはまったく同感である。
一方で、全く同感できないところもある。特に、ご本人は「周到に時間をかけて」退職準備を続けてきたと胸を張るのであるが、退職金の7分の1が税金で持って行かれたとか、求職しないと失業保険がもらえないとか、準備していれば当然知っておかなければならないことを分かっていない。さすが朝日新聞、そんなことを気にしなくていいほど退職金が高いんですねと思うだけである。
退職前後で一番気をつけなければならないのは、生活のリズムが乱れることである。中でも収入支出のバランスがくずれることは精神的にかなり大きいはずである。いま私が平穏に新年を迎えることができたのは、そのあたりの準備をおろそかにしなかったからだと思っている。
とはいえ、いま現在は、私も奥さんも働かなくても食べていけるけれど、いつかは想定外のことが起こって、さらに生活を切り詰めなくてはならなくなったり、何かしら収入の算段を付けなくてはならなくなるかもしれない。それでも、退職前には考えうる限りそうした不確定要素をつぶしていかければ、準備したとはとても言えないのである。
そのあたり、さすが大企業だけあって能天気である。そして、「パソコンやケータイは会社から借りていたので、自分で準備しなければならなくなって大変」というくだりに至っては、いったい読者のどれくらいの割合が同感すると思っているのか疑問である。それに、会社への依存度を下げましょうというご主張と、どう整合性をとればいいんでしょうという話である。
また、「節電ではなく、電気がないと思う」ことにして、帰っても電気を点けないというのもどうなんだろう。いまの日本でそこまでするのは健康かつ文化的な生活とは言えないし、だいいち水洗トイレもウォシュレットも使わなくて済むんですか、川に洗濯に行くんですかということである。奥さま雑誌でときどきそこまでやる人の記事が載っているが、どうもね。
おそらくそのあたりの評価軸、優先順位の付け方は、著者が独身のひとり住まいということに理由がありそうだが、そのあたりの経緯については全く触れられていない(別に、髪型がアフロだからどうこう言われても・・・)。そのあたりを書かないと、この人の書くことのどこまで自分も見習うべきで、どこからが事情が違うので一緒には考えられないか判断できないのである。
長いサラリーマン生活で、朝日・読売・毎日それぞれの新聞社の方々と仕事上のお付き合いがあったが、私の印象では、すべての業界をおしなべて、最も頭が良くて判断も常識的な人が多いのが新聞社である。著者は編集委員でもありかなり期待したのだけれど、同感だったところと同感できないところの振り幅が大きすぎて、ちぐはぐな読後感だったのはちょっと残念。
ところで奥さんの感想だが「もっと難しい文章を書く人かと思ったら、意外に軽かった」とのこと。さらに言うことには、「あんたから、会社を辞めた理由を説教されているみたいだった」とのことである。
[Jan 2, 2017]
高橋大輔「漂流の島」
同名のフィギュア・スケート選手が有名だが、こちらは探検家の高橋大輔。ロビンソン・クルーソーのモデルとなったアレクサンダー・セルカークの住居跡を発見した。その著者が、ジョン万次郎はじめ江戸時代に数々の漂流潭の舞台となった鳥島をリサーチした作品。
八丈島の南にある青ヶ島から小笠原諸島に至る南北約600kmの海域に、人が住める島は鳥島しかない。そして、江戸幕府は鎖国政策をとっていたから、長距離を航行できる船舶を作ることは禁じられていた。ひとたび海が荒れ帆や舵が壊れて航行不能になれば、船と乗組員は潮の流れと風向きのまま、太平洋の彼方に流されるのである。
その中で、たまたま鳥島に流れ着いた漂流民が何組かいて、そのまま帰れなかった者も多数いたのだが、中には運よく助け出されたり、船を補修・製造して脱出した者もいた。最も有名なのはアメリカの捕鯨船に助けられたジョン万次郎ということになるが、それらの漁民たちの足取り、真水もなく火もない中で最長19年も島でどうやって過ごしたのかを考察した本である。
著者は山階鳥類研究所の実施する現地の土木工事に、地熱調査の助手として参加することとなり、鳥島を実査することになる。あくまで助手の仕事が主なので行動は自由ではなかったが、かつて「漂流里」と呼ばれた江戸時代の漂流民の洞窟跡や上陸地を実際に見る。鳥島は明治・昭和の2度の大噴火により地形が大きく変わっており、目的とする洞窟は見当たらない。
唯一、島の西側にある溶岩地帯の崖に、防空壕の跡とされている2つの洞穴を見つける。中に入ってみると江戸時代の記録と似た部分もある。一方でかなり人の手が入った形跡もある。短時間では結論は出せないものの(結局、島には5日位しかいられなかった)、さらに調査すれば何か分かるのではないか、というところで島から引き揚げる日となる。
その後、東京都に対して調査申請をするのだが、かつて土木工事隊に入って鳥島を訪問していることが担当者の心証を害し、申請は門前払いとなり再度の鳥島訪問の目途は立たないというところでこの本は終わる。鳥島は島自体が天然記念物であり、アホウドリ保護以外の目的での入島は認められないというのが都の立場なのだ。
土木工事隊にはテレビのバラエティ番組も同行していたというから、著者にそれなりのコネか知名度があれば、おそらく何らかの形で認められたのだと思うが、それが日本なのである。誰か上の人が強い圧力をかければ芸人だって島に入れるし、そうでなければいくら意義を説明したところでどうにもならない。悲しいことであるが仕方がない。
天皇陵を調査すれば日本古代史が大きく書き換わることは間違いないのに、宮内庁は天皇陵の調査を一切認めない。現代の研究では本当に天皇陵かどうか疑問視されているのにそうなのだから、江戸時代の庶民が漂流して住んでいたのがどこかといった程度では、担当者が頑ななのも仕方のないことなのかもしれない。
あとは巨額の資金があれば、無許可で上陸するという手段はある。 実際、この本の中でも、天然記念物保護の原則から都が立入を認めなくとも、中国の漁船はこの近海に多数出没しており、台風や船の故障で避難したいと申し入れがあれば断ることはできないだろうと書かれている。とはいえ、たとえそうやって上陸できたとしても、その成果をおおっぴらにするのは難しい。
本筋とは別に驚いたのは、寛政時代に漂流して島に閉じ込められ、12年後に後から漂流してきた連中と船を作って脱出した土佐の「無人島」長平は、出航したのが赤岡で、墓はごめん・なはり線の香我美にあるということである。実は先日の四国遍路で、赤岡も通ったし、香我美の駅まで歩いてごめん・なはり線に乗ったのだった。事前に読んでいれば、ぜひ墓参りしたかったものである。
本筋の鳥島探究の話とは別に日本の役所の頑なさ、下に強く上に弱い体質を考えさせられる本でした。
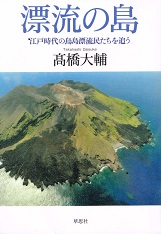
[Feb 6, 2017]
筒井功「日本の地名」
著者は共同通信社を42歳の時に退職し、以来「サンカ」を中心に民俗学を研究している。すでに齢七十ながら、コンスタントに著書が出版されるようになったのはここ十年ほどだから、最近といっていい。「新・忘れられた日本人」という著書もあるから、宮本常一を意識しているのは間違いない。なにしろ、軽トラで車中泊しながら全国を調査して回っているくらいである。
この本は「サンカ」とはあまり関係がないが、全国を調査で回った経験から地名を考察しているのでたいへん参考になるし、結論も妥当であると思う。最初は、副題である「60の謎の地名を追って」に引きずられて難読地名の研究かと思って読み始めたところ、日本の地名そのものの由来について考察する本だったのは予想外だった。
考えてみれば、地名が最初につけられたのは漢字も伝わっていない古い時代で、呼び名だけがあって漢字地名などなかったというのは著者の言うとおりである。そして、全国各地に似た地名が多いのは、もともとは地形や山・川・海との関係、定住した人達の職業などをもとに付けられた地名が多いというのも、考えてみれば当然である。
というのは、高速で移動する交通手段がない頃、歩いて行けない範囲に同じような地名が付いていても特に不便はなかったからである。それらを区別する必要が出てきたのは高速で移動したり広域を統治したりするからであって、歩いて移動できる範囲だけならそれほど多くの地名は必要ないし、そこに住んでいる人が場所を確認できればそれでいいのである。
私が思うに、地名(人の名前もだけれど)を記録する必要が出てきたのは徴税が発端だろうから、その時点つまり律令国家が生まれた時点で、呼び名だけの名前から漢字の地名が付けられたと思われる。いまでも奈良時代の木簡(字を書いた木片)が発見されることがあるが、たいていは租庸調に関する記録である。
その際、朝廷からは地名にいい字(好字)を付けるように命令が出されたというのは、この本を読んで初めて知った。「好字令」と呼ばれていて出典は続日本紀というから、リタイアしたら勉強しようと思いつつ未だ手をつけていない本である。元明天皇の和銅五年(713年)の発令だから、律令国家誕生直後のことである(大宝律令は701年)。
この著者の考察で優れていると思うのは、よくある地名由来伝説やアイヌ語・朝鮮語由来説は必ずしも妥当とは言えないと主張していることで、なるほどそうだと思う。ツルといえば判で押したように鶴の伝説が出てくるけれども、「ツル」というのは昔からある日本語で河岸段丘のことだと言われると、なるほどと思う。
古都・奈良の地名由来も、よく言われるのは朝鮮語の「ナラ」(国)が由来であるということで、私もいままでそう思っていたが、著者によると「ナラ」は「均(なら)す」と同じ語源の言葉で、平らになったところという意味が地名になったものだという。なるほど奈良は山に囲まれて平らになったところだし、全国各地に「奈良」地名があるのも納得である。
(百済は音で読むと本来ペクチェであるが、百済滅亡後に日本に移住した人達が「クン・ナラ(大きな国)」と称したので、日本においてはクダラと読むようになった。)
この本の指摘で認識を新たにしたのは、いまや日本語の語彙からなくなってしまった言葉というのはかなりの数あるということであり、その原因の一つが方言がなくなったことである。いまでは全国各地どこへ行っても標準語であるが、半世紀前だってそうではなかった。東京近辺と北海道だけが標準語で、あとの地域は多かれ少なかれ方言でしゃべっていた。
NHKが放送を始めてからテレビ・ラジオで流れている言葉が唯一の日本語ということになったとよく言われる。中国も同様の経緯があって、いまや北京語が共通語となりつつあるという。私などは、本来日本語にない二重母音を聞くだけでNHKの罪は大きいと思うのだが(命令をmeireiと発音するとか)、まあこれも時代の流れなのかもしれない。
そして、古事記や日本書紀、万葉集を読むと、いまでは使われなくなった日本語がたくさん出てくるということも分かった。いま出版されている万葉集の中には、何と読むか不明なので万葉仮名のまま印刷されている箇所もあるのだが、その中にはなくなってしまった言葉も含まれているのかもしれない。
逆にこの本を読んでいて耳ざわりなことは、「知識がないので断言できないが、私の考えを言えといわれればこうである」式の言い方がしつこく出てくることである。本というのは100%正しいことを書くものではなく(教科書だってそれは無理)、自分はこう思うということを論拠を示して述べるものだと思っているので、それは言わなくてもいいことなのである。
難読地名についての本かと思って読み始めたところ、日本の地名そのものの由来について考察した本でした。地名伝説の多くは後付けの作り話で、もともとは地形や山川との関係、住む人の職業が主だそうです。

[Mar 8, 2017]