高倉浩樹「極寒のシベリアに生きる」
伊藤薫「八甲田山 消された真実」 高倉浩樹「極寒のシベリアに生きる」 この本にいろいろ印象的なことが書いてあった。そのうちの一つが「文化とは事実上、自然環境に適応するために創り出された資源利用戦略だった」ということである。 伊藤薫「八甲田山 消された真実」 「八甲田山」はわれわれ世代にとってたいへん思い出深い映画である。 岡南「天才と発達障害」 いろいろ不満な点はあるのだが、最近読んだ中では、もっともインスパイアされた本のひとつである。 デヴィット・グレーバー「ブルシット・ジョブ」 いろいろなところで誉められている本なのだが、正直言って4分の1読まないうちに先が見えた。その大きな理由は、この著者の言いたいことは最初の16ページに尽きていて(最初にWEB投稿した論文)、あとはそれを水増ししただけなのである。読者にとって、まさに「ブルシット・ジョブ」(クソどうでもいい仕事)ではないかと思った。 F・H・バーネット「秘密の花園」 ここ数年、目が悪くなったせいもあって、字の大きな少年少女向けの作品を読むことが多い。 松本敏治「自閉症は津軽弁を話さない」 小田嶋隆のコラムに載っていたので借りてきた本である。題名と表紙のイメージからして、竹内久美子の教育版みたいなものをイメージしていたのだけれど、案に相違してきちんとした科学的分析である。 有馬頼底「禅僧の生涯」 最近、禅に関する本をいくつか読んでいるのだが、あまりに初心者向けかあまりに難解かどちらかで、自分の知りたいことにフィットした本がなかなかない。この本は、かなり知りたいことに近い本である。 山本作兵衛「炭鉱(ヤマ)に生きる」 国立国会図書館で閲覧した本なのだが、とても半日で読み切れる内容ではなかった。入手困難になる前に買っておこうと思ってアマゾンを探したら、定価1,817円送料1,250円の合計3,067円かかった。版元が講談社なのにえらく高いが、まあ仕方がない。
岡南「天才と発達障害」
グレーバー「ブルシット・ジョブ」
バーネット「秘密の花園」
松本敏治「自閉症は津軽弁を話さない」
有馬頼底「禅僧の生涯」
山本作兵衛「炭鉱(ヤマ)に生きる」
書評目次 書評2021(1) 書評2022
ネアンデルタール人が進出できなかったシベリアへ、現生人類は進出することができた。道具や毛皮などによる防寒対策、牧畜や海産物の利用による生活可能地域の拡大によってである。
筆者によれば、零下40℃とか50℃といった極寒の地にあっても、生活すること自体は想像するほど困難ではないという。穀物が育たないので農業こそできないが、牧畜に必要な草は生えるし、魚やアザラシなどの大型海獣が豊富だからである。
トナカイはサンタクロースの橇を曳く移動用の家畜だと思っていたが、そもそも肉や毛皮を利用するための家畜だった。寒冷地では、温帯で多く飼われている牛や馬、羊が耐えられないからである。いまでもトナカイ肉は売っていて、1kg300円ほどだそうである。
もともとシカ科の動物なので、食用にするには問題なさそうだ。むしろ、橇を曳かせたりする方がトナカイとしてはつらいのかもしれない。馬や牛は移動用・労役用に使われたが、シカ車というのは聞いたことがない。
この本の副題は「トナカイと氷と先住民」であり、トナカイともう一つ重点的に書かれているのは氷である。
人々にとって、どういう場所で住むにも飲料水の確保は重要で、まさに死活問題である。だから人々は清潔な淡水のある地域にしか定住できないし、水が手近に湧いていない時は井戸や地下水を利用してきた。
シベリアに住むひとびとはどうしているかというと、湖に張る氷を飲料水として利用しているそうである。冬の初め、厚さ50cmほどに厚くなった氷を切り出し、長方形に成形して地下倉庫に保管する。
地下倉庫は冷蔵庫よりずっと冷たく1年をとおして保管できるうえ、凍り始めの氷は不純物も少ない。給水車で生活用水が得られるようになった今日でも、氷取りは続けられ初冬の風物詩になっているそうだ。農業用水の必要がなく飲料水・生活用水だけの目的であれば、それで十分足りるという。
そういえば、「グーグーだって猫である」大島弓子の初期の作品で、ラップランドで幼少時代を送った少女の物語があった。
あれは確かスカンジナビアとかその方面だったが、本書の描いているシベリア少数民族と生活様式等で共通する点が多い。また、日本にかかわりの深いアイヌ民族やギリヤーク人ともたいへん近い。
トナカイを飼っていないだけで、サケなどの魚類やアザラシなどの大型海獣を食糧にすることや、穀物をあまり好まないことなども同じである。個人的に糖質制限を始めて以来、炭水化物をあまりとらなくても体調にそれほど深刻な影響が出ないことも分かった。
昔たくさんあって今ほとんど見ない本の一つが、こうした地誌、文化人類学の書籍のように思います。

[Jul 1, 2021]
もちろん、新田次郎の原作もすごいのだが、出演した役者が驚くべき面々だった。東映以外では初の本格的登場となる高倉健、犬になってしまった北大路欣也をはじめ、三国連太郎、加山雄三、小林桂樹、丹波哲郎、緒方拳、大滝秀治などなど。
他にも前田吟、藤岡琢也の渡世(わたせ)組、前千葉県知事森田健作、村人に加藤嘉、花沢徳衛、田崎潤といった名脇役陣。女性陣では栗原小巻、加賀まりこ、秋吉久美子に菅井きんである。よくスケジュールが調整できたものである。
映画「八甲田山」の出来が素晴らしかったため、多くの人はあれが真実だと思っている。しかし、新田次郎の原作が神田大尉、徳島大尉と名前を違えてあるように、本来あれはフィクションである。「仮名手本忠臣蔵」が赤穂事件のノンフィクションでないのと同じである。
だから、こういう題名で本を出すについては、<映画・小説から>消された真実という意味でないと読者には伝わらない。<報告書から>消された真実という意味なら、著者には一大事かもしれないが読者には関心事ではない。
現代の大蔵省だって報告書を改ざんして事実を隠しているのだから、百年前の軍隊で作成された報告書が事実をありのまま伝えているとは誰も思わない。それが問題でないというのではなく、そこをつついても仕方ないだろうということである。
著者はもと幹部自衛官であり、青森第五連隊にも所属していた。だから、われわれ一般人の目にできない資料も見ているはずだし、何しろ版元が山と渓谷社である。かなり期待して読み始めたのだけれど、残念ながら期待外れであった。
その第一の理由は、小説・映画の雪中行軍遭難事件の描き方でどこがよくないのか、分からないということである。
著者はあとがきの中で、「無能な指揮官の命令によって、登山経験のない素人が準備不足のまま知らない山に登山をした」のがこの事件の本質と書いているが、それは映画を見た人、小説を読んだ人の誰もが感じることである。
著者は連隊長(小林桂樹)が一番悪いといいたいのだが、連隊の責任者である連隊長の責任が一番重いのは当り前である。三国連太郎がいちばん悪いと印象付けるのは小説・映画の脚色であって、ひとりのせいで部隊ほぼ全員が壊滅した訳ではない。
(ちなみに、原作者新田次郎は、連隊よりも師団、さらに陸軍首脳部が一番よくないという意味のことを書いている。当然そういう考え方もあるし、著者のいう「(新田次郎の考えは)的を外している」という指摘の方が、私にはよく分からない。)
中隊長(北大路欣也)の計画もずさんなら、大隊長(三国連太郎)が直接指示したのも指揮命令系統を混乱させた。装備や準備が行き当たりばったりなのは映画のとおりで、遭難してからの対応もおかしい。何から何までめちゃくちゃなのである。その最大の責任が、現場にいた将校・兵士ではなく連隊長にあるのは間違いない。
映画・小説では、師団本部の命令ではなく希望ということにされているが、報告書等でも関係者証言でもそれは裏付けられていない。しかし、仮に著者のいうように弘前三十一連隊の八甲田踏破計画を耳にした青森の連隊長が泥縄で命令したとしても、遭難事故の本質は変わらないのではないだろうか。
「八甲田山」はわれわれ世代にとって、たいへん印象深い映画でした。ああいう映画はおそらく二度と撮れないでしょう。ただ、この本はちょっと期待外れ。

もちろん、もと幹部自衛官の考察であり、さまざまな資料を読み込んだ上の著作であるから、小説や映画とは違った点も当然ある。
例えば、3泊4日の大隊行動は連隊長決裁ではなく師団長決裁であり、第五連隊の雪中行軍は1泊2日で計画されたはずだとか、田茂木野で案内人の申し出を断ったというのは新聞の飛ばし記事だったとかは、新たな事実といっていい。
しかし、新田次郎の原作でも師団決裁云々の話は軽くではあるが触れられているし、仮に三本木(十和田市)まで踏破できたとして兵士はともかく橇や荷物をどうやって青森まで戻すのかという疑問がある。著者のいうとおり、もともと田代往復の計画だった可能性が大きいだろう。
しかし、それらは小説・映画を盛り上げるための脚色だったとすれば、事件の本質を大きく変えるものとはならない。確かに、雪中行軍の日に案内人を断ったのは脚色かもしれないが、計画段階で案内人の同行が却下されたことは十分にありえる。
著者はもと自衛官だから、軍隊の行動に民間人を同行させることに否定的だが、今日の感覚を百年前にそのまま通用できるかというと、できないだろう。現に、弘前隊は現地で案内人を手配しているし、この4年後に踏破された剱岳でも、陸軍測量部は案内人(香川照之)を同行させている。(「剱岳点の記」の原作者も新田次郎である。)
物足りなさのもう一つは、山と渓谷社が出しているのに登山としての雪中行軍の問題点をほとんど考察していないことである。
田代温泉への道を発見できず、3日にわたって食べるものもなく吹雪の中凍えていたのだから正常な判断が無理だったのかもしれないが、大隊長のグループ(三国連太郎と加山雄三など)は尾根から下りて沢を下流に向かっている。
これは登山の道迷いでは絶対にやってはいけないことで、大隊長以下が救助されたのはたまたまである。そして、加山雄三(のモデルになった将校)は、川を下れば青森に着くはずだと言って、いかだに乗せて伝達者を川から流したという。
その伝達者は、下流で遺体となって発見された。滝もあるし崖もあるのだから当然そうなる。このことは映画にはないけれども、小説にはちゃんと描かれている。
こうした事実はもっと掘り下げていいはずだが、著者にとって「命令はあったのか」「生存者が部隊の動向を把握していないのはなぜか」「組織上、中隊長と同行しているはずの将校・兵士が大隊長と一緒にいる」ことの方が関心事なのである。
そして、自力下山の直前まで達したのは尾根を進んだ北大路欣也グループだけで、三国連太郎・加山雄三のグループは、5日後に救助されるまで谷に入り込んで身動きがとれなかったのであった。
私がもっとも疑問に思ったのは、大隊長(三国連太郎)が同行せず北大路欣也の中隊が40人程度でやったとして、この計画は成功したのかということである。
200人近い死者は、今日に至るまで世界雪山事故のトップを独走する大事故であるが、30人だってぶっちぎりの国内記録である。指揮命令系統の混乱がなく、案内人を雇ったとしても、遭難をまぬかれたかどうか私は非常に疑わしく思っている。
というのは、新田次郎の原作にあるように「雪の中では地図が役に立たない」からである。この本の著者は当時の25万分の1地図では1kmが4㎜と書いているけれども、仮に25万分の1が25,000分の1だったとしても、迷うときには迷うのである。
「ホワイトアウト」の怖さは今日でもたびたび指摘される。コンパスを持っていても現在地が正確に分からなければ進路決定には役立たない。それでも、食料と燃料を十分持っているのだから、早めにビバークしていれば余力があったはずである。
そして、田代温泉というと大層な温泉地を想像するかもしれないが、実際には家族で経営する小さな宿で、200人の兵隊が全員泊まれる宿ではなかった。大部分の兵士は計画通り田代温泉に着いても野営せざるを得ず、田代まで行ったところで状況はほとんど改善しなかった。

つまり、遭難の最大の原因は「命令だから田代温泉までどうしても行かなければならない」というところにあって、結果夜間まで行動して田代への道は見つからず、夕食の配給が真夜中になってしまった。ちなみに、酒の配給もあったけれど変質して飲めなかったという。
「命令だから」が最大の原因だとすると、大隊長だからダメで中隊長なら大丈夫という理由は見当たらない。そして、案内人を雇ったから見つけられるかというと、それも疑わしい。7人の案内人を雇った弘前隊も田代温泉に達することはできず、八甲田山麓を強行突破するしかなかったのである。
それだけ、この日の風雪は激しかったということだし、行動すべきではなかったということである。そして、仮に案内人が「吹雪がひどすぎて無理だ」と言ったとして、指揮官がはいそうですかと演習をやめるかということである。
もちろん、ホワイトアウトの中、闇雲に前進させた大隊長の責任は重大だし、装備が全然なっていなかった(実は、カイロすら持っていなかったらしい)ことも大きい。しかし、雪洞を掘るなら地面まで掘り進めなければ焚火などできないことは分かりそうなものだし、それこそ事前に準備すべきことだろう。
また、部隊が四分五裂して脱走兵が続出したことに著者は憤っているけれども、映画を見て緒方拳が「俺は自分の歩きたいように歩く」という場面で、「敵前逃亡だ」と思う観客がどれだけいるだろうか。自衛官が疑問に思うことと、一般人が思うことは違う。山と渓谷社は自衛官向けに出版しているのだろうか。
徳島大尉(高倉健)の逆回り雪中行軍も、著者の評点は辛い。その最大の理由は、行く先々で天皇陛下直々の演習だと偽って援助を強要したこと、八甲田で案内人を先に歩かせ、青森が近くなるとあとは自分達で帰れと見捨てたことにあるようだ。
ただし、案内人への態度については映画でも小説でもきちんと表現されているし、渡した金額が少ないと著者が非難する意味が分からない(当時の日当5日分である)。確かに民間人を軍事演習に同行させるのは問題かもしれないが、4年後の剱岳で案内人を雇っていることは触れたとおりである(現在の国土地理院は当時の陸軍測量部)。
まして、山中で遺体や放置された武器等を見ているのだから、「けっして口外してはならない」と強く言ったり、自分達だけで到着したように偽装することはやむを得ない。むしろそう言わなかったとすれば、将校としていかがなものかという話である。
確かに、功名心があって目立ちたがりのところはあったのだろうが、それを人格的問題のように非難するのはかわいそうである。軍隊という組織内で上の階級を目指すため努力するのは、現代でいえば営業がセールス実績を上げるよう努力するのと変わらない。
そして、仮に著者のいうとおり高倉健のスタンドプレーで企画された雪中行軍だったとしても、それを認可した段階で責任は連隊なり師団にある。当初の企画意図がどこにあろうと、命令が出れば万難を排して実行しなければならないのは、当時も現在も変わらないのではないだろうか。
読み進めて思ったのは、山と渓谷社は元自衛官に書かせるのではなく、やっぱり羽根田さんに書かせるべきだったということである。
資料をもとに事実を考察し再構成する能力において、新田次郎と著者ではレベルが違う。せめて、山岳事故の観点を強調するとか考察の側面を替えないことには、この遭難事故について世に問うことは難しいだろう。
[Jul 23, 2021]
人間の認識・思考はいわゆる五感を通じて行われるが、その中でも情報量の多いのが視覚と聴覚である。大部分の人は聴覚が優先され、認識したことを脳内で言語に変換して考える。だが、視覚が優先され、映像で認識して思考する人もいる。
著者がまさにそのタイプで、記憶も思考も映像で行うので、言語で説明するのが苦手という。建築家として活躍しているのだが、この思考回路は三次元の空間把握に長けているので、建築家だけでなく、服飾・デザイン、外科医、パイロットなどに多いという。
一方、聴覚が優先され言語で考えるタイプの人は多く、学校教育も社会の仕組みもそれを前提に作られているので、社会適応がしやすい。学校で優等生とされるのはこのタイプである。
しかし、聴覚に偏りすぎた結果、視覚認識が十分にできずに空間の把握ができなかったり、他人の顔があまり区別できなかったりすることがある。顕著なケースとして、「不思議の国のアリス」の作者ルイス・キャロルが挙げられている。
われわれは基本的に自分を基準として考えるから、なぜこんなことができるのだろうとか、逆になぜこんなことが分からないのだろうと思うけれども、人それぞれで脳内の仕組みも体の使い方も違う。持ち点100点を攻撃力40守備力20すばやさ20運の良さ20に割り振る人もいれば、全部25の人もいる。運の良さ100あとは0だっているかもしれない。
著者はガウディとルイス・キャロルを例にあげるから、行き過ぎると発達障害と紙一重という結論になるけれども、必ずしもそうとはいえない。というのは、昨年読んだある本に、精神病といわれる病気の本質は、「心」の病気でも「脳」の病気でもなく、脂質の代謝異常という「体」の病気であるという仮説が示されていたからである。
認識あるいは情報処理が視覚に(映像に)偏っているか聴覚に(言語に)偏っているかは確率・分布の問題であり、発達障害はそれとは別の要因によるように思われる。ガウディが考え事に集中すると注意力が散漫になって、それがもとで路面電車に轢かれたというが、それは映像思考の人に限らず言語思考の人だってありえる話だろう。
そうした反論はあるけれども、この本を読んでよかったのは、「考える」とはどういうことなのか改めて考えさせられたからである。(「考える」を考えるとはちょっと妙ですが)
「考える」を学校のテストの類推でとらえると、まず「質問」があってそれに対する適切な「答え」を出すことになる。しかし、学校やテストがない頃から、人は考えていたはずである。
この本で述べられている例からとると、「言語思考」の人にとって「しりとり」が、「映像思考」の人にとっては「積み木」が、考えることの本質ではないかという気がした(あるいは、「積み木」もそうだが「あやとり」)。
さて、不満な点について述べると、この本はたいへん読みにくいのである。
具体的に項目をあげると、言葉の使い方(「間違える」の名詞形は「間違え」ではなく「間違い」)、接続詞の使い方、句読点の違和感、断定と推定の使い分けがおかしい、例の挙げ方が適当でない、論理展開が唐突などであるが、とにかく読み進めるのが苦行なのである。
著者と同じく視覚で考える人(映像思考)であったガウディ(建築家。サクラダ・ファミリアを設計した)には、綴りが違っているとか引用する場所を間違える癖があったというが、まさにその実例を見せられている印象である。
本当は、編集者なり出版社がそれを校正して読める本にして出版すべきところ、そのまま校正なしで出版されている。読書する人はたいてい言語思考だから、かなり違和感がある。あるいは、著者が手を入れるのを嫌がったのかもしれない。
題名と中身は異なり、認識と思考方法の違いについて書かれた本です。この題名は編集者に付けられたかな?

[Aug 3, 2021]
水増しした300ページ以上のほとんどは、WEB掲載後に読者から寄せられた投書である。「私はこんなくだらないことをさせられている」「ウチの組織はこんなにバカげたことをしている」といった内容を羅列したものと、著者のよく分からない分析である。半分過ぎからは、斜め読みで十分である。
そして、著者が「ブルシット・ジョブ」の例としてあげるところの、ほとんど仕事のない受付嬢とか、数mしか離れていない場所のパソコンを移動するために数百km移動する事務機器販売の下請けやら、会議や書類作りに労働時間の大半を使わなければならない事務職が、「どうでもいい仕事」とは私は思わないのである。
著者に言わせると、給料をもらうためにそう思い込んでいるだけというのだが、そうだろうか。会議や書類作成、ノウハウの必要な職務を外注することは会社のルールで決められており、その根拠は法律・規則であり、おおもとは損害賠償請求を受けないというリスクヘッジである。
社会の役に立っていないし、なくても誰も困らないというけれども、そんなことをいったら軍備だって同じである。世界中がいい人間ばかりなら警察も軍隊もいらない。そうでないから、なくてもいい仕事が次々と発生するのである。
さらに、著者は宣伝やセールスもやり玉にあげる。確かに、セールスはわずらわしいし、CMなどなければない方がいいと個人的にも思う。
けれども、資本主義の社会では自由競争・市場経済が大原則である。誰も宣伝せずセールスもしなければ、最初それを思いついた人間が無限大のメリットを確保する。多くの場合、一般消費者は不利だし不便である。
だから、宣伝やセールスは必要悪で、マーケットを効率的に動かすための必要経費とみなければならない。別に、上司を威張らせるために不必要な仕事を創出している訳ではない。
そしてもう一つの読み進めるのが苦痛な理由は、そんなにつまらない仕事なら、なぜさっさと辞めてより充実した仕事を探すよう仕向けないのかということである。
文句を言うだけで現状を改善しようとしないのなら、それは暴力亭主に泣き寝入りするDV被害者と変わらない。著者にとっては、DV被害の詳細をレポートすることと同様、ブルシット・ジョブの理論を紹介することに意味があるといいたいのだろうが、そんなことをしている時間があったら、すぐに逃げるようアドバイスした方がいい。
ケインズが1930年に予言した「週15時間労働」が実現していない理由を、著者は無意味な仕事ばかりが増えているためだというが、これは原因と結果が逆だと思う。無意味な仕事ばかり増えているのは、「週15時間労働」なんて誰もしたくないからではないだろうか。
以前、「年収90万円」の本を紹介した。その著者は、月に6万円あれば不自由なく暮らせることに気づき、バイトを週2日だけにしてあとは自分の好きに過ごすことにした。週2日のバイト、ほぼ週15時間労働である。
自分ひとり生きていくためには、いまの時代ケインズのいうとおりそれ以上働く必要はない。かつて、そういう場合には「神様が働くと決めている」というのが定番の理由付けだった。いま、神様も仏様も王様もいないので、みんなが好き勝手に動いてそうなっている。
「ブルシット・ジョブ」を暴力亭主と同様に説明したところで、得るものは少ないと思う。
アイデアはすばらしいが、400ページに及ぶ本書の核心は最初にWEBマガジンに掲載された16ページに尽きている。残り300ページ以上にふくらませた作業こそ、まさに「ブルシット・ジョブ」(クソどうでもいい仕事)では?
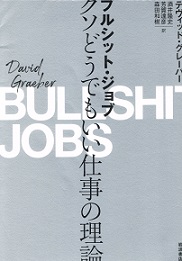
[Sep 7, 2021]
そうした本の多くは、言葉は悪いが子供だましのように思えて最後まで読まないでやめてしまうのだが、この本はたいへんすばらしかった。登場するのが子供達だというだけで、大人向けの作品ではないかと思うほどである。
作者のバーネットは、「小公子」「小公女」で知られる児童文学の大ベストセラー作家である。もちろん、それらの作品は子供の頃読んだのであるが、「秘密の花園」は題名のイメージから、これまであまり読もうと思わなかったのであった。
その本をなぜ読もうと思ったのかと言うと、梨木果歩が推薦していたからである。梨木果歩自身が、童話を書いているようでいて実は子供向けでないという作家なので、もしかしたら同じようなカラーなのではないかと思ったのである。
その通りであった。読み終わったとたん、というよりも読んでいる途中から、何度も前の場面を読み返したくなった。
この作品が発表されたのは1911年、第一次世界大戦前である。主人公の少女はインドに派遣された役人の娘で、王族のような暮らしをしている。当時、インドはイギリスの植民地だったのである。
そういえば、この作品より20年ばかり前になるシャーロック・ホームズのシリーズでは、相方のワトソン博士はアフガニスタン(!)から帰還した軍医という設定だった。当時はこういう設定がごく現実的だったのである。
この「秘密の花園」が安心して読めるのは、「悪意の人」がほとんど出てこないからでもある。世間一般には「悪意の人」だらけで、純粋な善意が背中から襲われることがしばしばあるけれども、この作品ではそういうことは起こらない。
あえて言えば、ポリティカルにコレクトでない発言を連発する主人公の少女が「悪意の人」に近いが、中盤以降善意の人になってしまう。その背景には自然があり神がいるというのが作者の言いたいことで、読者には自然に伝わってくる。
逆に、そうしたいわゆる差別発言がないと、この作品のニュアンスは正しく伝わらない。誰が誰をどのように差別していたか、それは何に基づく差別なのかを理解しないで、ただ差別はいけないと言われるだけでは、別の意味の差別が生まれるだけではなかろうか。
(ちなみに2000年以降の訳では、こうしたポリティカルにコレクトでない言葉は省かれている。でも、「私をインド人だと思ったって?」とか「あんたの背中は曲がっていると聞いたんだが。」では、ニュアンスが全然違うと思う。登場人物がそれで激高する理由も分からないし。)
その意味で、パラリンピックがNHKの1日の放送時間の大半を占めるというのは、どうみても悪平等である。契約上、オリンピックを放送してパラをやらない訳にはいかないのだろうが。
少なくとも、前回とりあげた「ブルシット・ジョブ」より何倍か勉強になるし、読んでいて楽しめる本である。
20世紀初めに書かれた少年少女向け作品ですが、年金生活者の親父が読んでもいまだにリーダブルです。
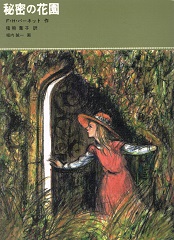
[Sep 23, 2021]
それもそのはず、著者は弘前大学教授で、大学付属特別支援学校の校長まで勤めたプロであり学者である。保健師の奥さんが「津軽弁を使う使わないで、自閉症かどうかのスクリーニングができる」というのを耳に留めて、研究を始めたのがきっかけであった。
著者は九州出身で北海道大学を出た特別支援教育の専門家。弘前大学に来た頃は津軽弁を理解することすらできない「渡来人」であった。「自閉症は津軽弁を話さない」という妻の言葉にも、それは抑揚のない自閉症特有の話し方でそう聞こえるのだろうと懐疑的であった。
ところが調べてみるとそうではない。方言の特徴にはイントネーションだけでなく、語彙(ボキャブラリー)、助詞の使い方などさまざまの側面があるが、自閉症児(者)の言葉を分析するとイントネーションだけでなく、語彙も助詞も方言とは違っていることが分かった。
著者は学者だから、学会などさまざまな機会をとらえて調べてみたところ、津軽以外の東北でも、関西でも、四国でも、ほとんど全国の方言を使うとされる地域で同じ傾向があることが分かった。「津軽弁を話さない」ではなく「方言を話さない」のである。
かつて「自閉症」と呼ばれていた発達障害は、アスペルガーや特定不能の広範性発達障害と合わせて、今日では自閉スペクトラム症と呼ばれている。昔はアスペルガーなどという言葉はなかったけれど、いまだったら私自身がそう診断されておかしくないので、ひとごとではない。
最近まで別の病気に区分されていたくらいだから、何が自閉スペクトラム症の中核的な症状で、何がそこから派生した症状なのかという点にも議論がある。現在では、コミュニケーション障害が主で言語の遅れが従であるという説が有力だけれど、過去には逆だという考え方もあった。
コミュニケーション障害とは何かと説明し出すときりがないのだが、私の理解では自分と他人の比重をどう取るかという問題である。私自身「私」の比重がかなり強いけれども、世の中の人には「他人」の比重が高い人も多いようで、だから「世間体」などという言葉もある。
しかし、サリーの課題(*)の例をみると、これが分からないのはコミュニケーションの問題ではないと思う。自閉症児の8割以上ができないと聞くと、その自閉症児がどのような合併症(知能など)があるか個別に議論しないと結論は出せないというのが第一感だ。
(*) サリーの課題
サリーはバスケットにビー玉を入れて部屋からいなくなります。サリーがいない間、いたずら者のアンはサリーのビー玉を取り出し、別の箱に入れて行ってしまいました。戻ってきたサリーは、ビー玉を見つけようとして、まずどこを探すでしょうか。
通常児は「自分が入れたバスケットを探す」と答えるが、自閉症児は「わからない」「アンが移した別の箱を探す」と答える例が多いという。
また、自閉症児(者)の教育現場でよく使われる方法として、指図するのに「座りなさい」「座ってちょうだい」と話すのではなく、「座ります」と言うとよく意思が伝わるとか、ホワイトボードに書いて指示するというのも初耳であった。
以前、統合失調症(昔は分裂病と呼ばれた)は「心」の病気でも「脳」の病気でもなく、必須脂肪酸の摂取障害という「体」の病気であるという仮説を紹介したことがある。
この本にはそこまで書いてある訳ではないが、「心」というものが自分と他者を区別するために脳が作り出した虚構(仮説)であることが示唆されている。だとすると、自閉症も「心」とか「脳」ではなく、「体」の病気である可能性がある。
中でもミラーニューロンあたりが怪しいような気がするけれども、そのあたりの解明は私が生きている間には無理だろう。
題名と表紙のイメージから軽いエッセイ風読み物を想像したのですが、中身はほとんど論文でした。統合失調症だけでなく、自閉症も「心」や「脳」の病気ではなく、「体」の病気ではないかと考えたくなる内容。

[Oct 21, 2021]
禅宗は日本では臨済宗・曹洞宗・黄檗宗が伝わっているが、いずれも中国の禅宗から枝分かれしたもので、その主要人物について解説している。
中国における禅宗は、いくつかの王朝による仏教弾圧(最近では中国共産党の)により、かつての隆盛はなくなってしまった。栄西や道元をはじめとする日本の留学僧が学んだ寺も、今日では荒廃して堂宇すら残っていない。そのあたりの訪問記も本書には採り上げられている。
ちなみに、カンフーの総本山である少林寺はもともと菩提達磨が開いた寺とされているが、現在では禅寺として機能していない(菩提達磨がカンフーを教えたということになっているらしい)。
禅宗を中国に広めたのはその菩提達磨(ボーディダルマ。日本ではだるまさんとして有名)で、5~6世紀に実在した人物である。ゴータマ・シッタータは紀元前5世紀の人であるので、シッタータから脈々と受け継がれたとしたら、千年間師匠から弟子へと脈々と受け継がれたということになる。
そのあたりの体系化を図ったのが達磨から6代目の六祖慧能で、達磨が釈迦から摩訶迦葉を経て二十八代、中国禅として達磨から慧能まで六代という今日でも残っている伝説を文書化した。
逆に考えれば、そうした正当化(正統化)を図らなければならない事情が慧能にあった訳で、それは先代である五祖弘忍(ぐにん)の高弟、神秀であった。則天武后の後援を受け、当時はむしろ神秀の北宗禅の方が勢力が強かった。京極堂の「鉄鼠の檻」にそのあたりのことが書いてある。
禅というと必ず出てくる有名なトピックが本書では説明されており、それらの逸話(公案)の背景もわかるようになっている。座禅する弟子の前で瓦を磨く話(南岳)や、仏像を焼いたのを非難されて「仏舎利をとるのだ」と答えた話(丹霞)、誰が来ても「茶を飲んでいけ(喫茶去)」とすすめる話(趙州)など。もちろん、狗子仏性、南泉斬猫、一日不作一日不食も出てくる。
思うに、鎌倉仏教の中でも天台宗に近い臨済宗や浄土宗は自らの宗派を外から見ることができるが、「絶対他力」の浄土真宗、「只管打坐」の曹洞宗、「南無妙法蓮華経」の日蓮宗にはそういった視点が希薄である。だから後の3教団は、教えを共有しない人達に分かるように説明することは苦手である。
苦手というよりも、その必要を感じないという方が近いかもしれない。信仰を同じくする集団の中でだけ分かる説明でいいのである。安土宗論で日蓮宗が浄土宗に敵わなかったのもそのあたりに原因がありそうだ。
一方で浄土宗・臨済宗は天台宗に近く、戒・律・禅や密教についても勉強するから、一般の人にも分かるように説明できる。そのあたりが、この本が分かりやすい理由のひとつかもしれない。
著者の有馬頼底和尚は臨済宗の高僧で、相国寺・金閣寺・銀閣寺の住職を兼ねる。名前からして有馬記念の有馬さんと関係があると思ったら、やはり親戚であった。久留米藩主で明治維新に至り華族となった。祖先をたどれば南朝方で活躍した赤松円心から村上源氏に遡る。
ただ、そういうたいへん偉い高僧であることから、「少さい」とか、現代では誤字になってしまう表現がいくつかみられる。誰も校正できなかったのか、もしかするとそれが「日本の禅」なのか、考えさせられてしまったのであった。
禅僧の生涯と併せて、禅宗の歴史を主要人物とともに追った本。禅宗のアウトラインをつかむのにかなり役立つ。

[Nov 25, 2021]
もともと、宮本常一の本に出ていた名前で、親子二代にわたって筑豊の炭田で長く働き、閉山になって昔のことを思い出しながら絵と文を綴ったものという。
本を買うまでまったく知らなかったのだが、山本作兵衛さんの作品はユネスコの世界記憶遺産に登録されているそうだ。そういう権威ある賞を得たにもかかわらず、氏は六百点に及ぶ作品をおカネに代えようとはせず、地元・田川市に寄贈したという。なかなかできないことである。
炭鉱というと、小学生の頃習ったのイメージが強かった。現場まで下りていく坑道はエレベーターやトロッコ、重労働だけれど地上に上がれば大きな風呂があり、映画館や商店など都会並みの施設が整っていると当時習ったのである。
ところが、この本によるとそうやって恵まれたのは閉山直前のわずかな期間だけであり、それ以前の半世紀は過酷な労働、前時代的な生活環境であったという。何しろ、犯罪者でもないのに「下罪人」というのが坑夫の別称だったそうだ。
現場に下りていくのも足なら、掘るのはもちろん人力。掘る人と運び出す人の二人一組で、多くは夫婦で組んだ。十二時間やそれ以上続く重労働で、もちろん落盤や爆発、出水の危険もある。夏目漱石の小説「坑夫」そのままである。
地上に上がっても、大きな風呂があるのは会社の偉い人だけで、一般の坑夫は大勢で1坪ほどの湯舟を共同で使わされる。炭坑で汚れた人達が入るので、もちろんどろどろ。それで男女混浴というのだからひどいものである。
この本に載せられている昔の炭鉱の作業や生活の様子、信仰、様々な験かつぎについては勉強になったけれども、この本の中でもっとも印象深かったのは麻生系列の炭鉱についてである。
いま大威張りしている御曹司上がりの政治家がいるけれども、麻生系列の炭鉱はもともと小規模で、信用もなかった。著者は、その麻生系列で長く働いていたのである。
炭鉱では、労働者に給料として切符と呼ばれる私設クーポン券を発行し、食糧や酒、生活用品は所内の購買部で切符と引き換えに購入するしかなかった。支度金として最初に支払われるのは現金だが、中に入ってしまうと現金は支払われなかった。
購買部に置いてある品々は高い割に品質が悪い。おそらく安く仕入れているのだろう。でも、他に買う場所がないので仕方がない。そういうところで労働者から搾取した結果が、のちに財閥といわれるほどの財産を積み上げ子孫を国会議員にできたのだが、当時は中小鉱山でまったく信用がなかったらしい。
炭鉱で暮らす分にはその「切符」で暮らすことができたが、何かの事情(親が死んだとか)で郷里に帰らなければならない場合、その切符は外の世界では通用しない。住友とか大手の炭鉱であれば切符を現金に代えてくれる業者はいたけれども、麻生ではとても無理である。
そんな具合だから、炭鉱内部の金貸しのような人が、半額とかで現金化してくれるのを利用する他に手段がなかったそうだ。そうやって労働者を食い物にしてのし上がってきた結果が、今日の大威張りになっているのである。そのうち罰が当たると思うのは、私だけではあるまい。
閉山まで筑豊の炭鉱で半世紀働いた山本作兵衛さんの画文集。国会図書館で閲覧しましたが、じっくり読みたくて購入しました。送料込で3,067円。

[Dec 8, 2021]