橋本治「権力の日本人」
ワイズマン「超常現象の科学」 橋本治「権力の日本人」「院政の日本人」 橋本治の本は、以前「九十歳になった私」を採り上げたけれど、軽い小説と小難しい時事評論ばかりだと思っていた。この本は、たまたま図書館で目について借りたのだが、久々に読み応えのある歴史本だった。歴史の好きな人にはぜひお薦めしたい。 リチャード・ワイズマン「超常現象の科学」 先月、「魂はない幽霊もいない」の記事を書いた時には、脳に関するいろいろな本を読んで考えたのだけれど、記事をupした後になって図書館でこの本を見つけた。 V.S.ラマチャンドラン「脳のなかの幽霊」 原題は"Phantoms In the Brain"。Phantomには幽霊とか亡霊という意味もあるのだけれど、ここで指しているのは脳の中で構成された幻影、幻肢(phantom limb)のことである。 原雄一「宿命 警察庁長官狙撃事件」 近年になって、国松警察庁長官狙撃事件に関する新事実が明らかにされている。この本は、当時事件を捜査した捜査第一課刑事(2016年方面本部副部長で勇退)の著書で、発行が講談社、2018年の初版である。 早瀬恵一「大本襲撃」 国松警察庁長官狙撃事件で、結果的に公安が事件解決の妨げとなったが、その源流ともいえるのが戦争前の特高警察の国策捜査である。 橘玲「スピリチュアルズ」 橘玲(たちばな あきら)の本は何度か紹介しているが、ものの見方・考え方が多角的で、最新の知見をフォローしている点が読んでいて楽しいところである。 田中康弘「山怪」 しばらく前まで、お盆の時期になるとTVでは怪談特集を必ずやっていたものである。稲川淳二くらいを最後に、いまではほとんどみられなくなってしまった。YouTubeでは都市伝説みたいのがたくさんあるが、ほとんどすべて見出しだけのアクセス狙いである。 篠田謙一「人類の起源」
21世紀に入ってまだ20年しか経っていないのに、人類の起源に関する研究はすさまじい速さで進んでいる。この本は、そうした経緯のおおよそを分かりやすく説明している。2022年、今年になっての新刊である。 米本和広「洗脳の楽園」 安倍元首相狙撃犯が、犯行前に真情を吐露する手紙をこの著者に送っていた。NHKや全国紙に登場するコメンテーターは信用できないが、この本を書いた人なら信用できると思ったという。 佐伯智広「皇位継承の中世史」 日本史に関する本も、近年新たな分析が加えられているものがあって面白い。この本も、物足りないところはあるものの、いろいろな観点から分析しているところが興味深く読めた。 遠山美都男「古代の皇位継承」 私が若い頃、20世紀末の古代史の本はほとんどがつまらなかった。基本的に日本書紀絶対、天皇は古くから神聖にして侵すべからずという論調で、古田武彦などキワモノ扱いであった。
ラマチャンドラン「脳のなかの幽霊」
原雄一「宿命 警察庁長官狙撃事件」
早瀬恵一「大本襲撃」
橘玲「スピリチュアルズ」
田中康弘「山怪」
篠田謙一「人類の起源」
米本和広「洗脳の楽園」
佐伯智広「皇位継承の中世史」
遠山美都男「古代の皇位継承」
書評目次 書評2021(2) 書評2023
副題が「双調平家物語ノート」(「双調」は雅楽の音階の一つだが、いわば橋本流という意味)なので、源平時代のことを書いてあるのかと思いきや、そうではない。最初は平清盛からスタートするけれど、時代は徐々に遡り、平安時代の政治はどう動いてきたかという話になる。
平安時代について書かれている歴史本はまず間違いなくつまらない。基本的に、藤原氏内部の権力争いと摂関政治がいかにして成り立ってきたかという話題がほとんどで、後の時代のような華々しい展開にはならないのである。
ところがこの本を読むと、そこには武家の戦争とは違った虚々実々の争いがあったことが分かる。武力闘争ではないけれども、政争の敗者は命を取られたり島流しに遭ったりするから、決して優雅な争いとはいえない。
認識を新たにしたのは清盛がどうして偉くなったかである。この本を読むまでは、福原(神戸)を拠点とした貿易による莫大な収益と、白河院のご落胤という政治力でのし上がったのかと思い込んでいた。
ところが実際には、清盛が殿上人になるのは平治の乱の後(1160年)で、その時清盛はすでに43歳である。それほど若くはないし、父である忠盛も殿上人になっているから(公家連中に妬まれた話が平家物語に載っている)、白河院ご落胤の恩恵はあまりなさそうである。
それ以前に、もし清盛がご落胤であると広く認識されているとしたら、当時政権を担っていた鳥羽法皇がよく思うはずがない。鳥羽法皇は、実は白河院の子で名目上自分の子となっている崇徳天皇のことを、「叔父子」といって嫌っていたのである。
だから、清盛が短期間で政権を把握したのは、貿易による財力の裏付けは間違いなくあったとしても、白河院云々はあまり関係なさそうである。それよりもむしろ、皇室内部の後継争い、藤原氏内部の権力争いに武力をもって介入したことが大きいように感じた。
そして、清盛が後白河院や関白以下を更迭した武力クーデター(1179年)にしても、その発端となったのは清盛が管理していた摂関家の財産を後白河院や関白が取り戻そうとしたことが発端で、貴族政治と武家政治の衝突という話ではなかった。
氏の考察は、そもそも現役の天皇が実権を持てば済むのに、なぜわざわざ院政などという手間のかかる二重構造にするのか、その発端はどこにあるのかという点に及ぶ。
とりあえずの結論は、奈良時代よりさらに前、飛鳥時代に遡って持統上皇がもとなのではないかということであるが、長年歴史の本を読んできた中で、平安時代史の考察をこんなに興味深く読めたのは初めてである。人生、死ぬまで勉強だと改めて思った。
平安時代の歴史について書かれた本は感心しないものばかりなのですが、これは読みごたえのある本。橋本治は軽い小説と時事評論ばかりと思っていたのですが、やっぱり才能あったんですね。

[Feb 2, 2022]
思わす、自分には予知能力があるのかと思ったが、もちろんそうでなくて、記事を書いた時に考えていた痕跡が脳のどこかに残っていて、関連がありそうな本の題名に注意を引かれたということであろう、それにしても、どんぴしゃのタイミングであった。
この本には、かつて超常現象と言われていたいくつかのケース、占い、幽体離脱、念力、霊界とのコミュニケーション、幽霊、マインドコントロール、予知能力について、実は脳の働きにすぎないということを最新の実験結果をもとに解説している。なるほど、心霊写真やこっくりさんを見なくなったはずである。(あと残っているのはUFOくらいだろう)
TRICKで阿部寛の役どころだった「本物の超常現象を見せたら賞金をさしあげます」というのも、米国で放送されたTV番組で実際にあった話である。1960年代に1000ドルだった賞金は1990年代には百万ドルまで引き上げられたが、いまだ賞金を獲得した人はいないという。
かつて心霊現象とか超常現象といわれた事象の多くはインチキ(注目を集めるためにトリックを用いた)であり、ポルターガイストなんてものはない。占いや読心術はコールドリーディングと呼ばれるテクニックであり、著者はこの本の中でタネ明かしをしている。
「人間は自分の見たいものを見る」というのは比喩ではなく、人間が進化する過程の中で、視覚から入ってくる膨大な情報の中から瞬間的に必要な情報を取り出すためにはパターン化をする必要があったからだという。
だから、幽霊を見たとか金縛りに遭ったとかいう経験者を調べると、そうしたパターン化の能力がすぐれていることが多い。つまり、獲物を見つけたり危険を察知する能力が高く、生き延びるのに有利な素質を持っていたということである。
よく言われる「この目で実際に見た」というのも、目から入ってきた情報を脳で処理した結果である。視神経では、白と黒、青と黄色、赤と緑は同時に見ることはできない。同じ視野で見たと思っているのは、脳で情報処理したからである。
だから、「見た」と思ったものは実際にあるものではなく、脳でそう認識したからかもしれない。他人に見えず自分にしか見えないものは、たいていそれなのかもしれない。目がいい加減なのではなく、脳の処理が個人個人で違うからである。
著者のリチャード・ワイズマンは英国のロンドン大学を卒業した大学教授で心理学を研究しているが、学者になる前はプロのマジシャンとして活動していたというから面白い。"wise man"(賢い人)という名ファミリーネームも芸名なのかと思ってしまう。
語り口は非常にフランクで、最初のうちは竹内久美子的な軽口コラムかと思って読み進めるのだが、実際は最新の実験結果や知見、科学者の共通認識を分かりやすく説明してくれる。その昔、超心理学に興味をもった頃を思い出してなつかしい本である。
「魂はない」の原稿を書いた後に図書館で見つけた本。自分で書いた内容を裏付ける内容だったのでびっくりした。とはいっても、私に予知能力があるのではなく、関心を持っていた分野なので目についたということでしょう。
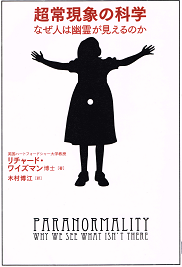
[Feb 17, 2022]
事故や手術で手足を切断しても、無くなったはずの指先、足先の感覚、特に痛みが残る人がいる。これは古くから報告されているのだが、つい最近まで、錯覚とか手足がなくなったのを認めないからだというフロイト的解釈がなされていた。
これに対し著者は、手足はなくなっても、脳の中の手足からの信号を感知する部分はそのまま残っていて、手足からの入力がないものだから近くに入ってくる感覚を手足からの信号と理解するからと考えた。
そして、手足からの信号を感知する部分はそれだけが独立してある訳ではなく、他のさまざまな部分からの信号(視覚とか触覚、手足以外からの信号)によって補正され、はじめて手足の感覚として認識される。
だから、脳の理解(すでに手足はない)と他の部分からの信号(身体に異状はない)が食い違うことにより、すでになくなっているはずの手足があるものとして感じられるのである。
これは、これとは逆のケース、つまり実際に手足はあるにもかかわらず、脳のその部分が損傷することによって、手足がないものと認識することで裏付けられる。こうした診断は、現代ではfMRIやPET、MEGといった機器によって、可視化されている。
だから、われわれが認識していること自体が脳において再構成されたもので、現実とバーチャルリアリティの境界はきわめてあいまいで、むしろ区別がつかないと著者はいう。もっともなことである。
この本は1999年の著作、つまり20世紀最後に発表されたものなのだが、脳に関する著作を調べると必ずといっていいほど参考文献にあげられている。すでに古典的名作といっていいかもしれない。
サイエンスライターであるサンドラ・ブレイクスリーとの共著になっているが、ブレイクスリーの担当部分は脚注で、ラマチャンドラン博士の見解がすべて定説ではなく、別の見解もあるという内容を書いている。これは、ラマチャンドラン博士がわざわざ意図して加えたものである。
この本の続編である「脳のなかの幽霊、ふたたび」や「脳のなかの天使」はラマチャンドラン博士単独の著作となっている。幻肢の研究から発展したさまざまのトピック、共感覚(数字に色がついて見える)や、踊るシヴァ神について新たに加わっているが、エッセンスは「脳のなかの幽霊」にほとんどおさまっている。
言われてみると、手足そのものはなくなったとしても、脳の中の回路までなくなった訳ではないというのは当り前のことで、最新機器がなくても想像できたはずである。
にもかかわらず、ラマチャンドラン博士が提唱するまで誰もそのことに思い至らなかったというのは、面白いことである。数学の世界で、わずか2千年ほど前にインドで「0」が発見される前は、何もない数を誰も想像できなかったことを思い出す。
Wikipediaでラマチャンドラン博士の顔写真を見ると、いかにもインド人という風貌である。彼らには、きっとそういった特異な才能が備わっているのであろう。
脳科学関係の本を読むと、必ずといっていいほど参考文献に入っている。1999年の著書だが、すでに古典的作品といっていいかもしれない。

[Apr 30, 2022]
2019年に平凡社新書から出ているテレビ朝日記者の「警察庁長官狙撃事件」と、内容的にたいへんよく似ている。いずれも真犯人とされる受刑者からの手紙や、捜査時の調書が元ネタだからある程度仕方ないが、地の文の書き方から表現からそっくりである。
刑事だから文章が苦手という訳ではなく、裁判官に提出する書類や容疑者の供述調書、出廷した際の想定問答集など作るから、民放の記者より文章は書いているかもしれない。両方読んでみて、内容的にもこちらの方がより深いように感じた。
オウム事件は、私が現役の間に身近に起きた最大の事件であった。サリンが撒かれた朝ももちろん通勤で、ニュースを聞いて驚いたし(幸い、地下鉄の路線が違った)、坂本弁護士は知り合いの知り合いである。江川紹子さんは高校の1年後輩であることを後に知った(直接の知り合いではない)。
地下鉄サリン直後に起きた国松長官の狙撃事件は、オウムの犯行だと誰もが決めてかかっていた。マスコミのみならず、警察もそう、世間の見る目もそうだったのである。幸い、狙撃された長官は緊急手術で一命をとりとめ、後にスイス大使に栄転した。実行者と目された信者も逃亡したまま逮捕されず、事件はそのまま時効となった。
ところが、現金輸送車を襲い、警備員を銃撃して負傷させた別の事件の捜査中、容疑者の住まいから長官狙撃事件の関係品が大量に出てきた。狙撃事件が平成7年3月、現金輸送車襲撃は14年11月、その間7年余、この男は捜査線上にも浮かんでいなかった。
その経緯については本書をお読みいただくとして、この男、昭和20年代に東大に入学するも中退(国松長官よりかなり先輩)、20代で職質した警官を射殺して無期懲役、40代後半で仮釈放されて、現金輸送車を襲撃した当時すでに70歳を超えるという驚くべき経歴だったのである。
40代後半で出所した元受刑者が、自分で食べていくだけでも大変なはずなのに、何度も渡米し、現地で武器の調達や射撃訓練を重ね、相当の費用をかけて支援者を確保している。それが事実とすれば、どうやってそれができたのかが個人的に最大の疑問であった。
この本によると、「武器調達に要した費用は3~4千万円。先物相場の利益や親の遺産を使った」となっている。武器はそのくらいかもしれないが、数週間から何ヶ月にもわたる米国渡航を年に何回もして、射撃訓練したり偽装のための工業製品輸出入などしていたら、とてもそんな額では済まない。
あるいは、本書で示唆されているように非合法薬品の売買益ということがあったのかもしれないし、昭和終わりのバブル期だから本当に先物や株の売買で儲けたのかも知れない。
とはいえ、40歳過ぎて出所した元受刑者が、東大に入る頭脳があったとはいえ億に近い資金を用意して革命に向けた活動を続けていたとすれば、その方が驚きであり、もっと掘り下げてほしい点である。
もし、資金の出どころが解明できない、隠れた支援者を特定できないとすれば、それで公判が維持できるのだろうか。捜査によって明らかにされた支援者も、元受刑者仲間とか、アメリカに渡ってカネに困っている連中とか、とても金づるになるようには思えない。
警視庁がオウム犯人説にこだわったのも、警察トップを狙撃して証拠も残さず逃走するには少なくとも複数の犯人で、しかも相当の資金力があると考えたからである。それが実は、単独犯に限りなく近かったということになる。
この本でも、テレビ朝日記者の本でも、どうやって資金を調達したのかについてはほとんど関心がない。個人的に相当もの足りなく思えるところである。
何か、題名と中身が合っていないような気もする。あるいは、真犯人である受刑者の希望した書名かもしれない。
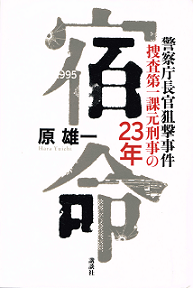
私の概算ではおそらく億を超える資金を、40歳過ぎて出所した元受刑者がどうやって調達したのかが最大の疑問という点まで書いた。
もう一つ違和感があるのは、真犯人の動機は何かにこだわっている点である。捜査官が動機にこだわるのは裁判官が要求するからだし、裁判官が要求するのは量刑の判断に不可欠だからである。読者の関心はまた別の話である。
本書では、最初の警官射殺で無期懲役となり、20年間を獄中で過ごさなければならなかった真犯人の逆恨み、私怨であると結論付けている。仮にそうであったとしても、その感覚は今日のものとはかなりの隔たりがあることを忘れてはならない。
というのは、いまから半世紀前、国家権力に対する反感は、いまとは比較にならないほど強かったからである。鶏か卵かという議論にもなるが、警察も高圧的で横柄だった。
「警察24時間、違法風俗店摘発」みたいな特番はないし、ハローワークの職員と派出所の警官の不親切には定評があった。学生運動で、機動隊より学生達にシンパシーを抱いていた人は少なくなかった(それが変わったのは連合赤軍リンチ事件である)。
現代でそれに近い感覚はというと、香港の民主化運動に対する圧力とか、ミャンマー、アフガニスタンの軍事政権に対する一般民衆の反感かもしれない。
警官を射殺すれば長期間刑務所なのは仕方がないことだが、本人は革命をしているのである。その気持ちは分からないでもない。単に人殺し逆恨みで片づけていいものでもないような気がする。
動機はまあがまんするとして(現代の感覚で考えれば)、仮に男を真犯人として起訴したとして、公判が維持できるかは別の問題である。
何しろ、証拠は本人の自白しかない。自己顕示欲が強いので自供をひるがえさないだろうということだが、それは検事でないから言えることで、私だったらそんな危ない橋は渡りたくない。
現場には、本人が確実にそこにいたという証拠はない(初動捜査が不十分だった)。凶器とされる銃も残りの実弾も、廃棄されてしまった(お茶の水あたりのお堀ではなく太平洋である)。共犯者はすでに死んでいる。本当に、自白だけなのである。
自白の任意性に問題がなく、秘密の暴露があるといっても、状況証拠だけでは公判維持は難しいように思う。せめて、事件後間もなくであれば目撃者もいたのだが、時効になるほど時間が経っていては証人だって記憶があやふやだろう。
そんなリスクを冒すくらいなら、幸い被害者は殺されなかったし、加害者は無期懲役2回で刑務所から出られる見込みはない。そうでなくてもすでに歳で(時効時点で80歳、2022年現在92歳)、長いことはない。真犯人はオウムだが証拠揃わずという判断はありえる。
オウム事件で指名手配された実行犯と目された男がまだ逃亡中だったことも勘案すれば、オウムが真犯人でないことを公表するメリットは、ほとんどなかったと考えても仕方がないかもしれないのである。
[May 12, 2022]
この本は平成に入ってからの著作なので、新事実や違った観点からの考察があるかと期待したのだが、残念ながらそうしたことは何も書かれていない。
そもそも、この本はどういう読者層を想定して書いているのだろうか。まさか、大本教団の広告宣伝のために書かれたのではないと思うけれども、絶対そうでないとは言い切れない。
極貧の家庭に育ち、口減らしのため小学校低学年の年齢で奉公に出た出口なお(開祖)。父が倒れ母が必死で暮らしを支える中、姉に続いて母も神がかりとなる。「お母もとうとう気が狂ったとみえる」と言われたところからすぐに教団ができてしまうから、読者にとって唐突な展開である。
治安維持法で弾圧を受けたのは特高による国策捜査だという論調だが、なぜ、2.26の反乱グループが大本に資金提供を求めたのか、なぜ、強制捜査に向かう京都府警が皆殺しに遭うかもしれないと緊張したのか、読者には何も背景が説明されない。
当時の大本がオウムのような過激な団体ではないと言いたいのは分かるが、それを具体的に裏付けてもらえないと読者は納得しないのである。
二代教主・出口すみ子が、強烈なキャラクターである母・出口みき、夫・出口王仁三郎を支えて教団の維持発展に寄与したことは分かるけれども、それだけで教団は大きくならない。何が信者を魅了したのか、時代性か、地域性か、そのあたりの説明がほしい。個人的には、教団の成長にはマルチ商法的要素が絡んでいることが多いと思う。
この本の主たるテーマではないけれども、特高警察による容疑者の取り調べ(拷問)がいかにひどいものだったかは、改めて認識しなければならない。
著者は、特高の課長が大本を訪問していたとすれば、王仁三郎や教団幹部と意気投合していたかもしれないとお気楽なことを書いているが、そんなことはありえない。
課長程度は国家権力からすれば下っ端もいいところで、命令されたことをするだけの存在である。だから、拷問でも何でもして裁判にまで持っていくのが仕事である。課長が手心なんて加えられないし、したら更迭されるだけのことである。
(合気道の開祖・植芝盛平も大本と関係があったが、彼の場合は軍隊・警察上層部と直接のつながりがあったので、連座を免れた。)
二代教主が獄中でゴキブリを話し相手にしていたとか、ほとんど大本事件とは関係ないことである。もっと重要でかつ今日でも考察しなければならないのは、大本教団の壊滅を図った国策捜査は必要だったかということである。
結果的に、裁判(それも戦前の)で治安維持法違反については無罪となり(不敬罪は有罪)、教団は今日でも存続しているのだから、必要なかったし実際壊滅できていないから失敗なのだけれど、「起こってもおかしくなかったことが、なぜ起こらなかったか」について、著者は考察していない。
最初の繰り返しになるけれども、この本が大本教団に買ってもらう目的で書かれた疑いをぬぐいきれないのは、そこが原因である。
毎日新聞出身の著者なので期待したのだけれど、新たな事実や違った観点からの考察はほとんどありませんでした。ジャーナリストだからといって、面白い本が書ける訳ではないみたいです。

[Jun 15, 2022]
この本は、近年のトピックであるトランプ大統領選勝利、イギリスのEC離脱国民投票可決という事件の背景に、インターネットのビッグデータを使った広報戦略があったことから話を始めている。
人間の性格は曖昧模糊とした複雑なものであり、単純化することなどできないと以前は考えられていた。ところが「ビッグ・ファイブ」と呼ばれる5つの要素でほとんどが説明できるというのである。
確かに、広報戦略という点では、この5つの要素さえ押さえればあとは些細なことだというのは分からないではない。しかし、橘玲自身が、ビッグファイブは異なる要素をひとつにまとめているのが不満で、本書では8つに拡大して説明している。説明のたびに拡大していては、「ビッグ・ファイブ」とはいえない。
数であれば5進法でも8進法でも、10進法でも16進法でもいくらでも表現することができる。だから、5つの要素で何かを説明することはできるだろう。しかし、リンゴ1個とみかん1個が違うように、すべて数の概念で表わせる訳ではない。
「ビッグ・ファイブ」が重視されたのは、資源というのは有限で、広告費にも広告期間にも制限がある。その中で、5要素でセグメントすることにより、最大の効果を期待できるところにあったからだと考える。
とはいえ、この本を読んで再認識したことがある。内向的/外向的というのは、最新の知見では刺激に対する反応が鋭敏かそうでないかと同じ意味だという。
例えば舌の上に果汁を一滴たらして、どのくらい唾液が出るかというきわめて即物的な方法でそれは判断できる。つまり、内向的/外向的というのは体質の問題なのだ。
体質の問題であれば、薬品を使うことにより変えることができるはずであり、実際にできる。同様に、ある性格はホルモンバランスによるし、ある性格はドーパミン受容体の遺伝子構造による。性格というものは、体質と同じことなのだ。
そうなると、以前書評で触れたいくつかの本にあるように、そもそも心とか精神とは脳の働きに過ぎないし、精神の病気は体の病気に他ならないということである。
あと、読んでいて気になったのは、この著者はベキ分布という言葉が好きでよく使うのだけれど、私が若い頃あまり使わなかった言葉なので違和感がある。正規分布とまったく違うものだという説明なのだけれど、正規分布を2乗するとカイ2乗分布で、これはベキ分布のひとつである。
つまり、正規分布とベキ分布はまったく違う分布ではなく、ベキ分布のひとつが正規分布なのである。一つの要素だけでアウトプットが決まるなら正規分布になるだろうし、2つ以上になると正規分布にはならない。要素が多ければ多いほどロングテール、つまり分布が極端になるのである。
帯に書いてある「私もあなたもたった8つの要素でできている」という訳ではないと思いますが、最新の脳科学の知見を分かりやすく説明した本です。個人的には、性格とは体質そのものだということが再認識できたのが収穫。

[Jul 6, 2022]
この本は山と渓谷社が出しているだけあって、現在では語り継がれなくなった山に関する不思議な話を集めている。著者は、全国の山間部を巡って猟師とともに野生獣を狩り、猟師や林業関係者、山麓に暮らす人々に聞いた体験談がまとめられている。
現在、そうした山間部でも年寄りが囲炉裏端で子供達に山の話をする機会はないという。野生獣自体、かつては毛皮や肉、あるいは薬として必要に迫られて狩られていたが、いまでは有害動物の駆除だけという。時代の流れとはいえ、もはや猟師やマタギだけで生計を立てる人はほとんどいない。
集められている話は、人魂や狐・狸に化かされる話、山の中の不思議な場所などに関するものが多い。リングワンデリングや誰もいない山中で誰かが自分を呼ぶ声がするという話は、登山者はしばしば耳にするものである。
私自身、ひとりで歩いているのに他の人の足音が聞こえたり、話し声が聞こえることがある。最近の脳科学の知見では、現実とバーチャルリアリティの境い目はあってなきが如きで、そんなことは普通に起こるらしい。
だから、例えばホタルやヤマドリ、自然にリンが発光したのを人魂とか火の玉と見間違えるのは当り前に起こることだし、まして昔の人達は恐ろしかっただろう。ただ、科学はそう指摘しても、山の奥深くには神が宿ると信じることは、誰にも止めることはできない。
もののけ姫の映画をみても、山の中に聖霊が現れるのをばかばかしいと思う人はそれほど多くはないと思っている。日本固有の八百万(やおよろず)の神々とはそうしたもので、ここに住む人達は一万年の長きにわたって、そう信じてきたのである。
だから山の中には不思議なことがあるし、すべて科学で片づけてしまう必要もない。とはいえ、かつて広く信じられていたのに、いまではまったく顧みられなくなった事柄について、改めて考えることには意味があるだろう。
私の子供の頃にはまだ、「狐憑き」とか「犬神」という言葉があった。わずか百五十年前の江戸末期に、四国のある藩で村人多数が狐憑きになった事件もあった。藩の正式文書として殿様にも提出されたものだというから、100%嘘ということはないだろう。
にもかかわらず、いまではそれらの言葉は死語になってしまった。もちろん、差別用語であるということもあるのだけれど、誰もキツネやイヌ、ネコが化け物になって悪さをするとは思わないからである。
だとしたら、なぜそのような症状となって表れたのだろうか。本書によると、「小さい頃からそういう話を聞いて育つと、そういうものがいる、そういうことがあると思い込んでしまう」からだという。
三つ子の魂百までという。幼い頃記憶されたさまざまのことは、長く本人の心身に影響を与えるということなのだろうか。
山と渓谷社が出しているだけのことはあって、単なる怪談話ではないところがいい。続編の「山怪2」「山怪3」も刊行されている。

[Aug 11, 2022]
20世紀の人類に関する研究は化石発掘による比較研究が主流で、北京原人、ジャワ原人、ネアンデルタール人など骨格の多くが出土した段階で、身体的特徴を通じて進化の方向を推測することがほぼすべてだった。
ところが、21世紀に入って研究の主体はDNA分析に移った。十年ほど前にネアンデルタール人のDNA分析によって、現代人の約3%のDNAがネアンデルタール人由来であることが発見された。ネアンデルタール人は絶滅していなかったのである。
DNAの3%といえば、先祖32人に一人の割合で純血ネアンデルタール人がいたことになる。五代母である。競走馬であれば、サラブレッドとはいえない水準になる。
(サラブレッドは8代前の先祖までサラブレッドでなければならない。だから半世紀前は、「サラ系」という馬が結構いた。皐月賞馬ヒカルイマイとか、第2回ジャバンカップの日本馬最先着ヒカリデュールとか。実際には、すべてのサラブレッドの先祖はアラブ種なので、DNA的にサラブレッドとアラブでそれほど違う訳ではない。)
なぜそうした分析が可能になったかというと、コロナでおなじみPCR検査という手法が開発され。コンピュータと組み合わせることによってDNAの分析が短期間に、正確かつ精密にできるようになったからである。
例えばコロナに関していえば、重症化リスクはネアンデルタール人のDNAをより多く持っている人でより高いらしい。日本での重症者が欧米ほど増えていないのは、日本人のネアンデルタール血量が多くないからだという仮説もある(ネアンデルタール人はヨーロッパが主な居住地)。
ネアンデルタール人は私の時代でも習ったけれど、デニソワ人はわれわれの時代には習わなかった。そもそも、デニソワ人の全身骨格が発掘された訳ではなく、化石の一部をDNA分析することによって、デニソワ人という種が認められたのである。
人類の起源に関する考察は、かつての化石発掘によるものからDNA分析に主流が移りつつある。そして、20世紀に定説とされたことのいくつかが、今日では否定されていることに驚く。

デニソワ人もネアンデルタール人と同様、現生人類(ホモ・サピエンス)と非常に近いが、いまでは絶滅したといわれている。確かに純血デニソワ人や純血ネアンデルタール人はいないのだが、われわれのDNAの約3%にその痕跡が残っている。
ということは、今を去ることわずか10~20万年前には(ヒトとチンパンジーが分岐したのは700万年前)、現生人類・デニソワ人・ネアンデルタール人が共存しており、子孫も作っていたということになる。最新技術で分析すると、発掘された人骨がネアンデルタール人とデニソワ人の混血とか分かるそうである。
そして、地理的に隔離された地域では、デニソワ人やネアンデルタール人の血量が3%よりかなり高い人がいまも存在するという。ただし、DNAに残っているだけで、遺伝的には出現しない仕組みになっているらしい。
子孫もできるしDNAも残るというなら、現代の人種とどこが違うのかという疑問が出てくるが、専門的には違うということのようだ。トラとライオンも混血にできるけれど、多くは繁殖能力を持たない。
このように人類の発祥に関する新たな知見が多く採り上げられている本なのだが、残念ながら時代がいまに近づくほど面白くなくなってくる。
その理由のひとつは、従来の知識から大きく変わったことがないからである。
例えば日本列島に縄文人がいて後から弥生人が入ってきたということはDNAを分析しなくても分かっていることで、特に目新しくない。日本列島に来る以前にバイカル湖にいたか中央アジアにいたかに、多くの読者はあまり興味がない。
人類の発祥がアフリカで、ある時期に「出アフリカ」して全世界に広まったこともDNA分析以前から分かっている。地続きだったか船を利用したかはともかく、コロンブス以前からアメリカ大陸に人は住んでいたから、何らかの手段で移動したのだろう。
もうひとつは、時代が下るにつれて、人間社会のダークサイドがより鮮明にみえてくるからである。インドではカースト制が原因で、もともとの居住地域がいまでもDNA分析で分かると聞くと、かえって興ざめする。
猿人とか原人の時代でも、殺し合いとか共食いとかは当り前にあって、けっしてユートピアではなかったはずである。しかし、古代文明以降に、知識や信仰の裏付けをもってそういうことをするのは、また別の問題であるような気がするのである。
[Sep 22, 2022]
いまや、マスコミに出てくる人達はみんなカネで動かされる。何を指摘するか誰に味方するか、多くの場合経済的利益によって決められる。だから、TVや新聞以外でも多くの情報を得ることができる現代は、正常な判断力を持つ人間にとって恵まれている。
この本の副題が「ヤマギシ会という悲劇」なので、ヤマギシ学園で虐待を受けた子供達の悲惨な話ばかりだったら嫌だなと思っていたのだが、大部分は「特別講習研鑽会」(特講)と呼ばれるヤマギシ会セミナーへの潜入取材である。
「ヤマギシ会という悲劇」という副題であるが、「悲劇」には、選択は間違っていないのに、時代の流れとかアクシデントとか予期できない事態で悪い方向にいってしまうというニュアンスがあると思う。
正直言って、ヤマギシ会に入るという選択が間違っているのである。だからこれは、悲劇ではなくて当然の帰結である。私だったら、「ヤマギシ会という苦界」と書くと思う。地獄でもいいかもしれない。
潜入といっても身分を隠してという訳ではなく、堂々と名乗って講習に参加した。運営側からは「取材ではなく自分のこととして受講してください」と注意を受けたが、それだけ彼らは自信を持っていたのである。
その「特別講習研鑽会」(特講)、執筆当時は毎月2回、80~100名の受講者を集めていたが、現在では年3回、20人定員である(幸福会ヤマギシ会ホームページ)。受講者数にして数十分の1、このペースで100年やっても300回にしかならない。ところがその当時、すでに1500回の特講が開かれていたのである。
受講の様子と受講生のその後でこの本の大半を占めるが、少し驚くのは、われわれの世代が受けた入社研修とか管理者研修とヤマギシ会の特講とで、共通する要素が少なくないことである。
日本を代表するような大企業と、宗教がかった組織が同じようなことをしていたのである。前者は、企業に忠実で法令を侵すのをいとわない社畜を、後者は、全身全霊どころか全財産を差し出すのをいとわない信者を作り出すためである。
著者の問題意識は、世間のことをひととおり知った上でヤマギシ会に尽くす大人は勝手にやればいいけれども、巻き添えになって社会から切り離される子供達がいたたまれないということである。
子供達は、いままでの地域からだけでなく父母からも離されて子供達だけのコミュニティ「ヤマギシ学園」に送られる。朝食なしの一日2食、まったくプライバシーのない24時間団体生活(布団は2人で1つ)、高校生の年齢になると朝から夜中まで労働である。
それだけならまだしも、園内には監視役からの体罰があり、上級生からのいじめがある。教団以外との付き合いは禁じられ、進路の希望も叶えられない。女子は高等部を出て2年経つと、「調正結婚」という名目で中年男と結婚させられる。
なぜこんな学園に、半狂乱になって入れたがる母親がいたのかまったく理解に苦しむが、ヤマギシにはまるのはまず母親からというケースが多く、父親は最初はしぶしぶである。ところが、特講を受け組織内の付き合いが深くなると、父親もそうなってしまうらしいのである。
Wikipediaによると、1990年代に社会問題化したこと、全財産寄付が脱税と指摘されたこと、実は有機農法でも無農薬でもなかったことが明らかになり販売が落ち込んだこと等により、教団は21世紀以降後退局面にあり、組織内でも改革が図られているらしい。
普通に考えて、ヤマギシ会の唱える「無所有一体」はユートピアである。貨幣がなければ最適な分配ができないし、無報酬労働では生産拡大ができない。いずれは個人も組織も再生産できなくなるのが理論の筋道である。
にもかかわらず教団を維持拡大できたとすれば、それはヤマギシの自然農法が市場を拡大したからではなく、新規入村者が寄付した財産を食いつぶしたからである。ネズミ講と同じで、拡大が止まれば破綻が待っている。
副題の「ヤマギシ会という悲劇」がしっくりこないが、教団に潜入して洗脳の危機を切り抜けながらのレポートは読みごたえがある。安倍元首相狙撃犯が、犯行前にこの人には真情を吐露した手紙を送ったという。

そして、数少ないトップ以外は余計なことを考える必要はなく、ロボットのように(あるいは養鶏場の鶏のように)朝から晩まで働いていればいいというのは、かつて毛沢東が文化大革命で言っていたのと同じである。
第一世代の生きている間はそれで何とかなるかもしれないが、それでは次の世代以降が育たない。卵だって有機農法だって万能ではない。時代が変わっても共同体を維持するためには、考えない人間ばかりいても仕方がないのだ。
著者は、創設者である山岸巳代蔵が何らかの宗教的体験をし、それを広めようと「特講」を始めたと書いているが、私は事実はもっと単純だと思っている。彼が養鶏場の鶏を見ていて、人間もこれでいいのだと思ったことが発端ではないか(ヤマギシ会の前身は山岸式養鶏会)。
だから、この組織も発足当時は食うや食わずで、他の農家から作物を分けてもらって何とか暮らしていけたが、食べるものもろくになく、生活水準もみじめなものだったらしい(一日2食とか1人6畳はその当時の名残りであろう)。
しかし、1970年代に学生運動に破れた連中が入ってから組織が変質した。生産は拡大し、理論構成も緻密になった。1Q84でふかえりが「ヤマギシは楽しかった」と言ったのは、おそらくそれ以前の組織である。
ヤマギシの村ですべてのものが共有だったり貨幣がないのは昔からだとしても、給料は渡さないものの実は払っていて、利益が上がらないよう操作しているとか、寄付された財産を組織に巧妙に付け替える作業は、おそらく彼ら団塊世代・全共闘世代の知識である。
だから、「特講」が私の過去受けた新人研修や管理者研修に似ているとしても、驚くにはあたらない。考えているのは同じような人間で、おそらく当時のアメリカ発の経営理論や能力開発からヒントを得たのである。
さて、それなりに考えて自分の判断でヤマギシに「入信」した親は仕方ないが、親の意思で訳の分からない学園に入れられてしまった子供達はどうなるのか。
本書の続編といえる「カルトの子」(ヤマギシの他、統一教会、エホバの証人などの子供達について書いている)の中で著者は、「子供を捨てた親はいずれ子供に捨てられる」と書いている。
ヤマギシ学園の子供達を調べた児童相談所の調査によると、子供達は身長で数cm、体重で数kg同年齢の子供より小さかったという。だからヤマギシの子供達が地域の小学校に通うと、「ちびっ子集団」と陰口を叩かれたそうである。
人類の歴史を紐解けば、核家族で父母に育てられた子供など現代だけで、多くは年上の兄弟や親類の子供が面倒をみた。個室なんてないし、風呂も食事ももちろん共同である。なのになぜ成長が明らかに遅れるのか。おそらく宗教には、そういう側面があるのだろう。
[Oct 26, 2022]
同じ吉川弘文館から出ている「皇位継承の古代史」という本があるのだが(亀田隆之著)、20世紀に書かれたものだけあって正直読むに堪えない。日本書紀は絶対に正しく、天皇は7世紀から神聖にして侵すべからずという観点なのである。
(吉川弘文館の同じような題名でも、遠山美都男の「古代の皇位継承」は相当面白い。改めて採り上げることもあるかもしれない。)
明治時代以降に皇室に対して一般人が抱いていたイメージと、平安時代以前に抱いていたイメージはまったく違うはずである。確立して100年とか200年の権威が、それほど神聖不可侵であるはずがない。
現代で考えれば、徳川将軍家の末裔であっても、選挙に出れば落ちてしまうということである。熊本藩はしばらく前まで殿様が知事や国会議員をしていたが、いまならどうなるか分からない。奈良時代の皇室だって同じようなものである。
大和朝廷のスタートは、豪族間の連合政権であったと考えられている。皇室も豪族のひとつであり、天皇家のトップつまり皇位も、他の豪族とまったく違う観点で選ばれたとは思えない。
私が考えるに、豪族のトップにはいくつかの要素がある。古代においては軍司令官であり、祭祀の主宰者であり、財産の管理者である。それらの要素が複雑に絡み合い、さらに対外的な代表者としての要素も加わってきただろう。
軍の司令官は基本的に男である場合が多いが、祭祀の主宰者は男女いずれかには限られない。財産の管理者なら、女性でもいいかもしれない。対外的な代表としてのトップは、3つのうちどの顔が重要であるかに関わってくるだろう。
だから、万世一系、皇位はいつの時代も神聖不可侵などという見方をしていると、いつまで経っても本質に近づけない。女帝問題も、そういった観点が不可欠であると思う。
この「中世史」は、2019年に書かれた本である。昔のように、天皇は偉いから皇族に生まれれば皆が皇位継承を目指しているという説明ではなく、人事権や財産権、裁判官や収税者としての役割など、さまざまな観点からの分析が加えられている。
特に、平安時代以降は皇室にも荘園主としての顔があり、そのことを考えなければ本質に迫れないという指摘は重要である。
例えば南北朝時代に北朝の財源となる長講堂領は、もともと後白河法皇所有の荘園群であり、財産上の権利とともに荘園管理を通じた主従関係ができているといった分析はたいへん重要である。
もともと皇位継承は、大日本帝国憲法も皇室典範もない時代から、「日本書紀」などに書かれた前例を基準として行われてきた。もちろん「Y染色体」の存在も知られていない。
その意味で、本書とは直接関係しないが、斉明天皇が道鏡を後継者に指名した事例や、足利義嗣の立太子がどういう理屈付けで行われたか、もう少し考えてみたいと思っている。
いろいろ物足りなく思うところもありますが、20世紀の分析とは違い、いろいろな観点から分析しているところが興味深く読めました。

[Nov 23, 2022]
あまりにも冷遇されたせいか、最後には本当にキワモノの「東日流外三郡誌」に行きついてしまったのは残念であったが、第二次世界大戦前の皇室絶対、大和朝廷は永遠ですというだけの見方に疑問符を投げかけたのは重要であったと思う。
そして、私の世代になってようやく、より自由な見方、事実はこうであったのではないかという推察が進んできたのはうれしいことである。この本も、「古代の」という題名ながら内容は奈良朝の皇位継承で、たいへん興味深い内容である。
私自身、「常識で考える日本古代史」で考察したように、大和朝廷が日本列島を代表する政権となったのは白村江以降であると考えている。少なくとも、「天皇」という名乗りは、天武天皇の時代、日本書紀が作られて以降である。
百歩譲って大和朝廷が白村江以前から日本を代表していたとしても、大化の改新から数十年、聖徳太子の時代から百年ほどしか経っていない時代と、少なくとも千数百年皇室が続いているいまとでは、皇室に対する見方は違う。
著者の見方はまさにそういうことで、天智系と天武系の対立というのは後付けの理屈で、当時の天皇周辺はそんなことを考えていなかったとする。まったく同感である。
それでは、何を考えていたのか。少なくとも持統天皇周辺は、近親結婚の積み重ねで濃厚な血の後継者を作り、その子孫に皇位を継がせようと考えていたという。
これは、現代の考え方からするとたいへん危険だが、当時の人達はそんな保健理論、近親結婚で病気が起きやすくなることなど知らない。しかしそう考えると、天智・天武期前後に、現代では忌避される近親結婚が繰り返されていた理由を説明できるのである。
それを無知だとか前近代的で片づけられないのは、現代でも競馬の世界で、3×4の近親交配(インブリード)で走る馬が出るなどと言われている現実をみれば分かる。もっとも、最近あまり言われなくなったようだ。
そして、「大鏡」に書かれているように藤原不比等の父親が藤原鎌足ではなく天智天皇だとすれば、さらに近親婚の度は進む。事実かどうかは分からないが噂があったのは間違いないので、そういう意図で奈良時代の後宮は成り立っていたということになる。
だから、いわゆる天武系の聖武天皇や孝謙・称徳天皇は、自分達の王朝の始祖は文武天皇とその父草壁皇子だと考えていたという。草壁皇子の父は天武天皇、母は持統天皇、妻は母の異母妹・元明天皇である。近親婚の始まった時期である。
題名は「古代の」だが、内容は奈良時代の皇位継承について。よくいわれる天智系と天武系というのは後付けの理屈で、当時の天皇はそんなことを考えていなかったとする。同感である。

さらに、孝謙・称徳天皇(重祚したので諡号が2つある)が独身であったため彼女の死によりいわゆる天武系は断絶するが、もともと聖武天皇(孝謙・称徳天皇の父)は天智系とか天武系とか考えていなかったという指摘は重要である。
聖武天皇は「この国の権力も富も私のものである」と言って奈良の大仏を作った絶対君主で、藤原氏出身の光明皇后の尻に敷かれた病弱の天皇というイメージは正確でない。
だから、娘に天皇を継がせてその後どうするか考えていなかったとは思えない。絶大な富と権力があるのに、自分が死んだら良きに計らえなどと言う訳がない。皇后の言うがままということもありえない。
それについても、娘(孝謙・称徳天皇の異母妹)の生んだ孫に継がせるつもりだったと指摘している。光明皇后と藤原氏がいるので、おおっぴらに言うことはできなかっただろうが。
孝謙・称徳天皇の異母弟妹は3人いて、そのうち安積親王は若くして亡くなり、井上内親王と不破内親王が聖武天皇より長生きした。聖武天皇は、井上内親王か不破内親王の生んだ孫に皇位を継承させるつもりだったのである。
これは十分ありうることで、絶対君主である聖武天皇に天智系だの天武系だのの区別はない。y遺伝子なんてことも知らない。自分以外はすべて臣下であり、身内は草壁・文武の血を引くものだけという考えである。
ずっと後の江戸時代、やはり絶対君主であった将軍徳川綱吉は、兄の子である家宣でなく娘婿である紀州家に将軍を継がせようと思った。それで家宣は紀州を目の敵にし、ライバルの尾張家を贔屓にしたのである。
ところが、あまりに近親結婚を続けたのがおそらく原因となって、草壁・文武系統には体の丈夫でない天皇や皇子が多かった。だから、長生きできず子孫も少なく、それ以外の天武系の皇子が、たびたび謀反を起こしたり疑われたりしたのである。
絶対君主・聖武天皇は、孝謙・称徳天皇の後、娘婿である塩焼王(印西ゆかりの松虫姫こと不破内親王の夫)か白壁王(井上内親王の夫。のちの光仁天皇)を中継ぎとして、自分の孫に富と権力を残したかった。
ところが、聖武の死後、光明皇后と孝謙・称徳天皇はまったく違う方向に進むのである。
光明皇后は権力基盤を維持するため、自分以外が生んだ聖武天皇の娘やその孫に皇位は渡したくない(実は、光明皇后の母の親戚ではあるのだが)。だから、甥にあたる藤原仲麻呂やその庇護のもとにある大炊王(淳仁天皇)を重用するのである。
孝謙・称徳天皇は父である聖武天皇のワンマン性格を受け継いで、自分以外はすべて臣下という考えであった。
聖武天皇の遺志は無視できないが、腹違いの妹に義理は感じていない。白壁王や塩焼王のように娘婿ではないが、自分の見込んだ道鏡は言ってみれば娘婿のようなものだから、それで皇位に就けようとするのである。
しかし、道鏡の皇位継承は成らず、聖武の子と孫である井上皇后、他戸親王は光仁天皇(白壁王)を呪詛したとして殺される。もう一人の娘婿である塩焼王も、それ以前に藤原仲麻呂(恵美押勝)の乱に連座してやはり殺されている。
そうしたアクシデントと藤原氏の策謀により、結果として皇統はいわゆる天智天皇系に移るのであった。
[Dec 27, 2022]